
三 人 展
平原辰夫・橋本賢治・岡村光哲2007.4.13(金)-4.19(木)
12:00〜19:00まで
(但し最終日は17:00まで)
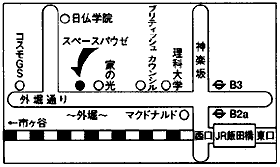 gallery space pause
gallery space pauseギャラリー スペース パウゼ
〒162-0826 新宿区市谷船河原町9
会場 tel 03-3269-5007
事務所 TEL/FAX 03-3269-7008
●JR飯田橋(西口)、地下鉄有楽町線、南北線(B3,B2出口)より徒歩5分
信号一つ目手前
作品画像および地図をクリックすると拡大されます
さて、もう十二月ですね。今個展の準備中です。来年の1月28日から2月2日まで、あと2ヶ月もありません。去年と同じ銀座のギャラリーSOLです。今回はどんな作品になるか、まだはっきり見えてきませんが楽しみです。あれこれと迷って決めかねていますがどうなりますか。しばらく集中します。
ラジオを聞きながら製作中。いろんなニュースがありますね。
謝罪会見が多いですね。謝罪か?一見
身分なき共犯。おねだり体質 。 妻の権力は夫の権力に比例する。虎の威を借るなんとやら
あまり強くないけど品行方正な横綱や、たいして面白くないけど人格者の芸人を見たいか?
霊界霊視オーラ迷信占い スピリチュアルなショー売?
僕はスピリチュアルって神聖なものだと思っていたが、粗製濫造大安売り。
徴兵制で若者を立派な社会人にできる? どげんかせんといかんのは若者だけか?
こんな事言い出す知事自身もね。
先生は集めたみんなの絵を次の図工の時間に返してくれた。でも何枚か手元に残していた。その中から森君の絵を最初にみんなに見せた。校舎の窓や周りの木の枝など、細かい所までしっかり見て描いていると、先生はにこやかに言った。何をやっても優秀な森君のことが、まるで自分の事のように誇らしげだ。森君の絵が褒められるのは当然だ。良く観察しているから、全ての物が在るべき位置に正確に在る。恐竜だって飛行機だって、いたずらで描く先生の似顔絵だってうまいんだ。でも次にコージの絵を見せられて驚いた。
先生はあんな絵のどこを褒めるつもりなんだ。池を描いているけど、いつも見ている池には見えないし、色だって混ぜこぜだ。岩の上の亀だって、丸い眼が無ければ岩とまったく同じだし、鯉なんて赤い干物にしか見えない。先生は言った。このバナナの葉を良く見なさい。一枚一枚全部違う色で塗られているでしょう。同じバナナの葉っぱだから同じ色だと頭で決めつけないで、目で確かめる事が大事なんです。先生はそう言うけど、僕にはやっぱりよく解らない。少なくともバナナの葉はあんな色じゃない。茶色や黄色で塗るなんて僕には考えられないが、コージの奴は特別だからあんな風に見えるのかもしれない。コージは自分の絵が褒められても知らん顔だ。先生の言葉と、自分の絵と、自分とがどこでどう結びついてるのか理解しかねているようだった。そして次は僕の番だった。
僕は恥ずかしかった。笑い者になりそうな僕のヘタな絵をなぜみんなに見せるのだろう。茶色と赤と黄色のクレヨンが無くなりそうなので、節約の為にこの三色は主に線を引く為だけに使った。広い画面を塗るには指でけちけち擦り付けるしかなかった。指の力が入り過ぎて画用紙の所々が毛羽立っている。幸い青色はたっぷり残っていたので、瓦の屋根だけは時間をかけて塗り込んだ。先生は僕の絵を初めて褒めてくれた。指で擦り付けた淡い色が画面のほとんどを占めている中に、くっきりとした青い瓦屋根が強い印象を与えていると先生は言った。
僕はコージの気持ちが解るような気がした。僕だって自分の苦し紛れの方法と、先生の褒め言葉とが素直につながらないんだ。婆さんに良く描けてると言われた時は意外でちょっと嬉しかったが、先生に褒められても恥ずかしいだけなのはどうしてだろう。自分のいい加減な行為を、きちんとした言葉で褒めてもらうなんて、絵以外ではあり得ない。自分ではまったく意図していなかったことを、褒められて喜んでいいのだろうか。解っている事は、僕はこの方法をもう二度と使わないということだ。
僕は「傘の婆さん」の家を描く事にした。きょうの図工の時間は、教室から出て好きな風景を描くのだ。みんなそれぞれ好きな場所を選んでいいのだが、絵に描きたい場所を突然捜せと言われても困る、という子が多かった。いくつかの仲良しグループは話し合いながら場所を決めていた。校庭にとどまって、古い木造の校舎や校庭の隅のプラタナスの木を描く生徒達もいた。コージはさっさと自分の遊び場所の池に向った。あいつは絵なんて興味ないから何処だっていいんだ。先生に描く物を指定された方が楽だと陽介が言った。描きたい場所がなかなか決まらない陽介を僕は誘った。
あまり学校から離れてはいけないと先生に言われている。でもあそこまでなら大丈夫だろう。あまり乗り気じゃないが、陽介は自分では場所を決めかねているので僕の誘いに乗った。僕らはベニヤの画板と画用紙を抱えて、文房具屋の横の狭い道を歩いた。両側から竹や木が覆いかぶさってトンネルのようだ。陽が射さないのでいつも湿っぽい道だ。僕らは靴が泥で汚れないようにつま先立って歩いた。そこを抜けると雑草の生い茂った空き地があって、隣に婆さんの庭がある。手入れの行き届いた庭の入り口には、僕の背丈の倍もあるウチワサボテンが、黄色い花をいっぱい付けていた。棘だらけのサボテンは婆さんにそっくりだ。いつでも誰も信用していないような上目使いで、にこりともせず人を見るんだ。その眼で、サボテンの棘のように自分を守れると信じているようだ。
婆さんは年寄りなのにおかっぱのような髪型をしている。ほとんど真っ白の髪なのに、おかっぱだなんて女の子みたいじゃないか。足腰が弱いので遠くに出かける事はない。遠出するのは近くの小さな商店街に買い物に行く時だけだ。どんなに天気が良くても、杖の代わりに竹の柄のついた傘を必ず持って出かける。庭でもその傘を杖にして、草花の手入れをして、飼い猫か野良猫なのか区別のつかない6匹の猫の世話をしている。一緒に住んで自分の世話をしてくれている娘より、猫や草花や傘と過ごす時間の方が長いのかもしれない。時々、猫に話しかけるように草花にも話しかけているから、傘にだってそうするのだろう。これは独り言じゃなく会話なんだ。
以前、コージが庭の植木鉢を蹴ってひっくり返したことがある。眉間の深いシワを、ますます深くしてコージを睨みつけた婆さんは、いつも肌身離さずにいる大事な傘を槍のように投げた。傘は力なく花の苗の上に落ちて届かなかったが、眼から発する激しい怒りはさすがのコージにも届いた。いつもは曲がった腰が、その時はすっと伸びて体がひとまわり大きく見えた。それ以来、コージは婆さんをからかうのを止めた。怒りの本気の度合いを、コージほど理解できる子は他にいないんだ。
婆さんの家は半分藁葺きで、建て増しした半分が瓦の屋根だ。僕らの地方では瓦はほとんど黒だが、珍しく青い瓦を使っている。白い豚を初めて見た時と同じように、こんなものがあるのかと驚いた。笑顔を忘れて、疑わしそうな上目使いで世間を見ている頑な婆さんの家に、こんな新しい屋根は似合わないと思ったが、でも僕が興味を持ったのは確かだ。でなきゃ陽介をこんな所に誘ったりしない。陽介はサボテンが気に入ったらしく、緑のクレヨンで描き始めた。クレヨンのこんな太さでは細い棘を描けないと文句を言った。僕もクレヨンを取り出した。茶色と赤と黄色をよく使うので、それぞれあと二センチ程しか残っていない。母に頼めば買ってくれるだろうが、家の貧しさを知っているので言いにくい。ちょっとでも、困った母の顔はできれば見たくないんだ。
僕らは空き地の石に腰掛けて描いていた。ふたりとも実にたどたどしい手つきだ。僕は画用紙の真ん中に婆さんの家を描いた。右の青い瓦屋根ばかりに気を取られていたので、他の部分がおろそかになった。庭にいた猫も3匹描いたが、動物園でも見る事のできないほど珍しい小さな怪獣みたいだ。陽介のサボテンは大胆だ。たくさんの黄緑の楕円形が画用紙からはみ出して、画板にまでいっぱい跡がある。先生はいつも、思い切って感じたように描きなさいと言う。でも多分、陽介の大胆な絵より、大人が描いたようにまとまった、森君の上手い絵を褒めるんだろうな。僕だって写真みたいに描けたら嬉しいけど、写真に勝てるわけがない。なぜこんな無駄な競争をするのだろう。漫画を描いてる方が余程マシだ。
青いクレヨンで瓦を塗り終えた時、後ろに人の気配を感じた。夢中になっていたので気がつかなかったが、いつの間にか傘をつっかい棒にした婆さんが立っていた。買い物の帰りなのだろう、持った風呂敷包みからネギがはみ出していた。婆さんは探るような眼でふたりの絵を見比べた。僕も歳をとったらあんなに固まった顔になるのだろうか。いつもの苦々しい表情なのでけなされるかと思ったら、良く描けてると言った。ひょっとしたら、眼が悪くて自分の家が描かれているとは思わなかったのかもしれない。僕の描いた婆さんの家は、いびつな茶色の四角い形と、執拗に塗り込まれた瓦の青い色があるだけだったから。
婆さんはあめ玉をくれた。僕らが声をそろえてお礼を言うと、ちょっと眼をつぶった。長い間忘れている笑顔を思い出そうとしたのかもしれない。深いシワが額や口元に刻まれて老木のようで、白いおかっぱの頭はススキの穂だ。僕のおばあちゃんは、僕が生まれるずっと前にもういない。自分の先祖をさかのぼって想像するのは、なんだか不思議だ。だって、数えきれないくらい多い先祖の、誰か一人でも欠けていたら僕はここにいないんだ。僕も歳をとって、父のようになりおじいちゃんのようになるのだろう。この婆さんにも、母親のおっぱいを飲んでいた頃があって、僕らのような子供の時があった筈だ。跳んだりはねたり、笑いあったりふざけたりした子供の時の記憶は、婆さんの何処に仕舞ってあるのだろう。体を支える為に傘の杖を持つ事になるなんて、女の子だった頃の婆さんは想像もしなかっただろうな。
庭で遊んでいた猫達を引き連れて、婆さんは家に入って行った。一匹だけ胸に抱かれた白い猫が、婆さんの肩越しにこっちを振り返った。遠くから見ると白い髪と猫の境界が解らない。ずっと変だと思っていたけど、今解った。あのおかっぱの髪型はきっと、女の子でもあり娘でもあった自分を忘れないためなんだ。
僕は暴力なんて大嫌いだ。喧嘩をして勝った事を自慢する奴がいるけど、子供の僕でさえ、そんなの子供っぽいと思うんだ。自己主張の言い争いもつまらない。どうやら僕には、是が非でも主張しなければならない自己なんてものがないんだ。コージは長々と悠長な口喧嘩なんかしない。奴の場合はいきなり手が出る。自分よりずっと大きな年上の男の子をぶん殴って泣かせても、自慢なんてしない。もっとも奴にとって、そんなの自慢する程特別な事でもないというに過ぎないのだろう。手足とか背中なら解らないではないが、眼でも鼻でも口元でも腹でも見境なく殴るなんて、僕には全く理解できない。僕は喧嘩なんかしない、というよりあんな事出来ない。無理にでも相手を言葉や暴力でやり込めようとするなんて、そんなものに僕は嫌悪感しか抱かない。
近所の子とふざけて取っ組み合いになった事がある。僕は右肩を強く押されてよろけた拍子に、倒されないように思わず相手の腕をつかんだ。するとその子の方が倒れてしまって、道端の石のお地蔵さんにぶつかった。おじいちゃんが生まれた頃よりもっと古い時代に作られたのだろう。お地蔵さんの顔は雨風に削られてのっぺりしていた。彼は前につんのめって、このお地蔵さんの胸のあたりに頭をしたたか打ちつけた。同時に、供えてあった赤い菊の花の首が全部折れた。額にうっすら血が滲んでいた。額に手を当てて血が出ているのを知ると、その子は急に泣き出して僕に殴りかかってきた。ワザとじゃないのだからそれはないだろうと思った。困惑している僕は相手の手を振り払おうとしたが、結果的に顎に拳骨がまともに当たってしまった。泣き声がさらに大きくなった。
泣きながら帰るその子の後をとぼとぼ歩きながら、泣きたいのはこっちの方だと思った。これは喧嘩でもなければ暴力でもない。全く僕の意志ではないんだ。ついさっきまで仲良く遊んでいて、今だって僕は仲良くしたいのだ。殴りかかってくるなんて思いもしなかった。痛みもあるけど、少しだが出血している事に驚いたのかもしれないし、血に対する恐怖感に似たものもあったのかもしれない。でもこれは事故だ。それなのに僕に対する怒りになって暴力にまでなるなんて理不尽だ。なぜこんな事になってしまったのだろう。すごく悔しくて悲しくなった。うつむいて歩きながら、ついに僕も我慢できずしゃくりあげた。泣き声はなんとか抑えたが、言いようのない悔し涙はなかなか止まらなかった。うちの近くまで来た。泣いた顔を母に見られたくないので、家の下を流れる川で顔を洗った。上着の袖で顔を拭いて、赤とんぼの空をしばらく見上げながら涙を乾かした。あの子の額に滲んだ血も赤く、菊の花も赤く、赤とんぼも赤い。おそらく、今の僕の眼も赤いのだろう。
自分の声がこんなに薄っぺらな声だとは思わなかった。こんな声でみんなに話しかけていたのかと思うとがっかりした。重々しい声が欲しいとは思わないが、やっぱり変な声だ。先生が国語の時間にテープレコーダーを持って来た。僕らは全員で教科書を少しずつ読んでテープに録音したのだ。そして再生したのだが、自分の声なのに聞き覚えがなかった。知らない他人の声のように聞こえた。自分の声と自分自身の間に薄い幕を張られているみたいだ。自分の声が再生される度に、みんながくすくす笑ったり顔を見合わせたりした。朗読がうまいとかへたとか、漢字を間違って読んだというような事より、みんなが自分の声自体に興味を持った。
授業中にこんなにもみんなの眼が輝いているので、先生は満足そうだ。いつもは教室がざわつくと、静かにしなさいと怒るのだが今は笑っている。たぶん先生も自分の声で試したのだ。そして、こんな威厳のない声でいつも授業をしているのかと、ちょっと残念に思ったに違いないのだ。
僕は自分じゃない自分を捜している時がある。おとなしくて真面目で先生のお気に入り、そんなものから脱皮したくなる。僕はみんなが思っているような生徒じゃない。絵日記には嘘を書いたし、スイカ泥棒だし算数の宿題をしない怠け者だ。森君みたいに優秀な生徒になりたいわけでもないし、ましてやコージみたいな乱暴者なんてまっぴらだ。具体的にこんな自分になりたいというイメージは浮かばないけど、でも自分がこんな自分であることにもやもやした苛立を感じているんだ。まわりから、お前はこんな奴だと鋳型にはめられるのは嫌だ。だいたい、人の性格なんて便宜上勝手に思い込んでいるに過ぎないと思ったりする。
僕も他人の事を言えた義理ではない。コージは乱暴で陽介はちょっと暗くて、園田は出しゃばりで森君は面倒見が良くて、河村さんは活発で小野さんは落ち着いている。こんな風に僕だって、みんなの事をそんな性格だと勝手に決めつけているんだ。テープを再生して自分の声を聞いた時のように、自分自身に対する違和感をみんなが感じているのかもしれない。ひょっとしたらコージだって、自分の荒れる感情に戸惑って、穏やかな優しい性格を夢見る事があるかもしれない。みんなが無い物ねだりをしているのだろうか。
僕は学校帰りにたまに海辺の方を歩くようになった。カッちゃんの家に行ってからのことだ。山育ちの僕に海は新鮮だ。山際の集落とは反対方向だから随分遠回りになるが、広い海はぼーっと眺めているだけでささやかな幸福感に包んでくれる。煌めく満天の星空もそうだ。なぜあんなに星は瞬くのだろう。地上の人間の事などには無関心な星空がなぜ慰めになるのだろう。でも、解らなくてもいいんだ。窮屈な言葉の意味付けなんてつまらない。澄み切った星空が僕の真上にあって、僕は見とれていて、ちょっぴり神秘的な気分に包まれている。それで充分だ。だけど、それにしてもとまた考えてしまう。銀河系の直径が十万光年だっていわれても、日常の生活で何をどう考えたらいいんだろう。星座の本を思い出しながらとりとめのない想像をしては、小さな自分がますます取り柄のない存在に思えてくるけど、不思議と惨めな気分ではない。クラスの誰かと比較して小さな自分を意識したら惨めになるけど、相手は宇宙だもの。むしろ爽快で、コージのわがままや算数の宿題を呪う事さえ忘れてしまう。
風は吹いていたが日差しは穏やかだった。僕と陽介は港の方を回って帰る事にした。文房具屋の前をいつもと反対の右に曲がった。左側の屋根越しに川がきらきら光っていた。川と海が出会う少し手前に大きな老木の楠が悠然と立っている。樹齢五百年と言われている。潮風や台風に耐えた遥かな時間が、太い根元から細い枝にいたるまで威厳を与えている。父や母やおじいちゃんや、そのまたずっと先祖達もこの木を見ながらこの道を通ったことだろう。この町の歴史を全て見てきた老木に見守られながら、僕らは港への橋を渡った。橋の上は風を遮るものがないので、川風と海風が一緒になって陽介の黄色い帽子を吹き飛ばそうとした。あごひものお陰で助かったが、脚の悪い陽介はよろけて僕のランドセルにぶつかった。ランドセルにはカッちゃんに貰ったウミガメの卵をふたつ入れていたので、潰れた卵で中の教科書もノートもべっとり濡れていた。でも、それに気づいたのはうちに帰ってからの事だった。
橋を渡ってすぐに不思議な動物を見た。まるまる太った豚だった。近所でも豚を飼っている家が何軒かあって、豚自体は珍しくもなかった。でも白い豚なんて初めてだ。僕らの地方で飼っているのはみんな黒豚だ。タンポポは黄色で、炭は黒で豚も黒というのは僕の常識だったから異様な動物に見えた。おじさんが、手に持った棒切れで豚を操りながら散歩させているところだった。品評会にでも出すのだろうか、体中きれいに磨き上げられている。見慣れている黒豚よりひとまわり大きい、はち切れそうな肉の塊がゆらゆら歩いているのだ。僕は陽介と顔を見合わせて、ふたりの小さな常識が壊れたのを確認しあって口元だけで笑った。僕らの住んでいる町なんて世界の断片に過ぎないのだ。広い世界には白いタンポポも白い炭も豚も、白い夜だってあるのだろう。
僕らは港まで歩いた。海の底を覗き込むと青く果てしなく深く、ずっと見ていると吸い込まれそうになる。星空と同じように奥深く神秘的な世界だ。でも表面はいつもの風景だ。岸壁に係留された漁船が小魚たちに突つかれながら、ゆらりと揺れてしばしの休息をとっている。カモメ達は餌を求めて飛び交っていた。食い意地の張った彼らは、食べるという欲望のためだけに白い翼を使っているかのようだ。朽ちた廃船は斜めに横たわって、かつて駆けた広い海原を懐かしく思っていた。船名も雨風に消され、錆び付いた船体はそれ自体が自らの墓標のようだ。
僕らはいつもの決まった帰り道を外れていることだけで愉快だった。それ以外の目的なんてなかった。学校で習った歌やデタラメの即席の歌など歌いながらぶらぶら歩いた。先生は真っすぐ帰りなさい、道草を食ってはいけませんと言うけど退屈な日々にささやかな刺激は必要なんだ。先生達はどうしているのだろう。橋のたもとにできた飲み屋に行ったりするのだろうか。想像もつかないが、先生も酔っぱらって僕らみたいにデタラメの歌を歌うのだろうか。それとも海や星空を見上げるのだろうか。大人になったら海や星空なんて必要ではなくなるのかもしれない。大人は何でも知っていて何でも確実にこなせるのだから、僕のように空想の世界に迷い込む事なんてしないのだろう。
北の空が急に暗くなってきた。さっきまで晴れていたのに、海の向こうからにわかに灰色の空になってきた。カッちゃんの家の辺りの上空はもうすっかり暗くなっている。海も防波堤もテトラポッドも橋も夕方の景色のようにくすんできた。空から降ってきたのは雨ではなかった。噴火した桜島の灰だ。大量の灰が風に吹き寄せられて僕らの小さな町を襲ったのだ。防波堤もテトラポッドも橋も道も家々も、細かい灰色の粉に覆いつくされた。僕らは港の工事現場に立っている小屋に避難して、奇妙な粉が音も無く降り積もるのを見ていた。現役の漁船もたちまち廃船と同じように古びて、緑の木々は枯れ木のように生気を失って見えた。車が通るたびに橋の上の粉は川面に舞った。
僕らは小屋で待つしかなかった。陽介は小屋から手を突き出した。持っていた帽子を受け皿にして灰を受け止めた。ほんのわずかずつではあるが灰は帽子の底に積もっていった。僕は砂時計を思い出した。確実に過ぎて行くのに、眼には見えない時間を僕らは黄色い帽子の中に見ていた。
カッちゃんが突然僕の家にやって来た。日曜日の昼過ぎだった。こんな山の方まで来たのは初めてだと言った。自転車を買ってもらったのだ。嬉しくてつい遠出して、町からこんな所まで来てしまったらしい。僕らは学校では一緒にいる事が多かった。ふたりには特に共通するものなど無かったが、何となく馬が合った。学校の外で遊ぶ事はなかった。学校からはそれぞれ反対方向だったからだ。学校では家の事など話す事はなかったから、お互いの家庭の事など何も知らなかった。カッちゃんは大体の見当だけつけて道を聞きながら、よく解らない山道を僕の家までたどり着いたのだ。坂道もあるしでこぼこ道だし初めての道だ。
僕はみすぼらしい自分の家を、カッちゃんに見られるのが恥ずかしかった。仲がいいだけに余計に恥ずかしいと感じた。家は古いし囲炉裏の煙で煤けた家の中は暗いし、障子には猫の爪の跡があって、土間には下駄や靴が脱ぎ捨ててあった。母は、お昼時だから食べていきなさいと言ってうどんを出した。野菜が少しだけ入っていてほとんど具のないうどんだ。僕とカッちゃんは土間の上の板敷きの所に並んで座り、脚をぶらぶらさせながら食べた。父も田んぼから帰ったままの泥のついた服で、少し離れて座って食べていた。
埃っぽい土間には午後の陽が差し込んで、かまどの丸い影が父の足元に伸びていた。かまどには大きな釜が乗っていて、牛の餌になるサツマイモが煮えていた。時々草に混ぜてやるのだ。開け広げた戸口からの穏やかな風が僕らの半ズボンの脚をくすぐった。カッちゃんは自転車の事を嬉しそうに話して、父と母も小さな珍客の話を笑顔で聞いていた。町の方から僕の友達がわざわざくる事なんてなかった。カッちゃんはきれいに食べ終わると母にどんぶりを渡した。にこにこして美味しかったと言った。あとはお茶だけだった。甘いお菓子もジュースもなかった。
ひと月くらい経った土曜日、今度はカッちゃんが僕を自分の家に誘った。カッちゃんの家は県道から少し横道に入った食堂だった。後ろには砂浜と海が広がっていて、八百屋と豆腐屋の間に割り込むように建っていた。薄いプラスチックの看板が出ていたが文字はかすれていた。一階が店で二階が住居だ。二階に上がってすぐ右手の戸を開けるとカッちゃんの部屋があった。自分の部屋があって好きなように使えるなんて羨ましかった。机の横の本棚には漫画や絵本が並んでいた。メンコやビー玉を入れたお菓子の空き箱の上に、新しい飛行機のプラモデルの箱も何個か積まれていた。僕らは腹這いになって漫画を読んだ。
うちでは漫画なんて買ってもらえなかったので、発売されたばかりの新しいものを読んだ事がなかった。友達に借りて、月刊誌に連載の鉄人28号やまぼろし探偵や赤胴鈴之助を何回も読み返した。続きを読むのにひと月以上待たなければならなかった。週刊誌の漫画が発売されると聞いた時は疑った。でもそれは本当だった。僕はおそ松くんや、特に伊賀の影丸に夢中になった。でも友達に借りるしかないので、週刊誌になっても月刊誌と同じように待ちくたびれた。半年か一年も経ってボロボロになった漫画を友達に貰う事もあった。大事に長い間取っておいた。気に入った場面を見ながら広告の紙の裏に鉛筆で丁寧に模写した。そんな時、母は僕が真面目に勉強していると思っていた。
階段をとんとんと上がってくる音が聞こえた。カッちゃんのお母さんがラーメンを持ってきてくれた。お母さんは太っていて、血色が良くて元気そうな人だ。
熱いからゆっくり食べなさいと言って、割烹着の前で手を拭きながら忙しそうに食堂に戻って行った。彩り鮮やかなエビや貝や野菜が大盛りのごちそうだった。こんなもの僕は食べた事がなかった。いつもカッちゃんはこんなものを食べているのか、僕は聞いてみた。きょうは特別だよとカッちゃんは照れたように言ったが、うちのうどんとは大違いだ。あの粗末なうどんが美味しかった筈はなかった。カッちゃんは優しいなと思いながら、僕はまた恥ずかしくなった。
お腹いっぱいになった僕らは海の方に行った。コンクリートの堤防を乗り越えると、潮の香りと魚の干物の匂いがした。浜のあちこちには大小の流木が散らばっていた。海水で漂白されて、まるで動物の骨のように見える物もあった。ブイやプラスチックの容器や木の箱や缶詰の缶なども打ち上げられていたが、外国の文字が書かれているものも多かった。僕は本の挿絵で見た嵐の海の難破船を想像した。難破船からは沢山の人や積み荷が海に放り出され、その一部がこの砂浜にたどり着いたのかもしれない。カッちゃんは朝鮮半島からも流れ着くんだと教えてくれた。確かに漢字でもひらがなでもない文字があった。丸と棒線を組み合わせたような文字だった。僕は地図を見た事はあったが、前に広がる海とその向こうにある世界が実感できなかった。僕らは裸足になって波打ち際で波と遊んだ。僕らの足元を濡らしている海が世界中の海につながっていて、僕らと同じように子供達が波と戯れているかもしれない。今自分の触っている水が、見知らぬ世界とひとつにつながっていると思うと不思議な気分だった。
遠く右手に釣り人がひとりいて、あとは数羽のカモメと波だけで浜は静かだった。僕らは並んで乾いた砂に寝転がった。背中にさらさらの暖かい砂を感じながら、頭の後ろで手を組んだ。この砂浜には亀が産卵に来て、ピンポン球のような卵をいっぱい産むんだとカッちゃんは言って、食べた事もあるんだよと付け加えた。雲のない青空にくっきりした輪郭の三日月があった。新品のナイフみたいに鋭利だ。あの月が落ちてきたら、堤防の横に立っている堅いヤシの木だってすっぱり切れてしまうだろう。
カッちゃんは、大きくなったら食堂のお母さんの手伝いをするんだと言った。カッちゃんにお父さんがいないのを初めて知った。交通事故で亡くなったらしい。お父さんの事はおぼろげに憶えているだけだから、時々写真を見ては確認したり思い出したりするそうだ。カッちゃんは学校にいる時より大人に見える。
図書館の本や漫画にうつつを抜かしている僕より、ずっと懸命に生きてるんだ。僕はおとなしいから真面目だと先生もクラスのみんなも思っている。近所の大人にもそう言われてきた。だけど、おとなしいのと真面目とはまったく違う事だと、薄々僕は気づき始めている。多分、カッちゃんみたいに現実を考え懸命に生きている人を真面目と言うんだ。僕は空想の世界にふわふわ浮かんでいるばかりで、現実なんて何も見えていないんだ。
僕は立ち上がった。そろそろ帰らないと山の集落に着く頃には暗くなってしまう。カッちゃんも立ち上がって、服の砂を払い落として先に歩き始めた。カッちゃんはふざけて大股で飛ぶように歩いた。そんな歩き方をすると亀の卵が潰れてしまうよ。僕は笑いながら言った。僕よりずっと大きなカッちゃんの足跡は砂浜に深く残った。僕はその足跡を一歩ずつゆっくり確かめるようにたどった。堤防を乗り越えて、さっき寝転がっていた場所を振返って見た。陽の落ちかけた砂浜にはひとり分だけの足跡が続いていた。
転校生は女の子だった。細い身体が先生に隠れるように教室に入って来た。彼女の淡いピンクのワンピースに教室が急に華やいだ気がした。みんなの視線を意識しながら、無理にでも笑顔で対応しようと考えているような表情だった。先生に自己紹介するよう促されると彼女は真っすぐ顔を上げた。意志の強そうな眼だが、誰にも視線を合わせず後ろの壁を見ているようだった。彼女の第一声をみんなが興味津々で待っていた。河村美津子です。名前を言ってから両肩を少し上げて深呼吸した。やはり緊張してるんだ。歌が好きです。ピアノが得意です。仲良くして下さい。それだけ言うとお辞儀をして先生の方を見た。ふたつに分けたおさげ髪がちょっと不満そうに揺れた。考えてきた事の半分も言えなかったというような顔だった。
先生は小野さんの隣を指して席に座るように言った。コージの近くでなくて良かった。女の子同士だし小野さんの隣で良かったと僕は思った。図書館で背の高い小野さんをよく見かけた。手も脚も長かったので、僕には届かないような高い本棚の本を楽に取り出していた。本の最後、背表紙の内側に薄茶の紙袋に入った図書カードがあって、図書館で本を借りる時は名前を書くようになっていた。そしてカードは図書館に預けた。僕が借りようと思う本のカードには必ず彼女の名前が書いてあった。いつも僕より先なんだ。ルパンやホームズやシンドバットやほら吹き男爵の本を借りようとしたら、もうカードに名前が書いてあった。ロビンソン漂流記や十五少年漂流記もそうだった。若草物語や赤毛のアンや小公女みたいな本なら解るけど、こんな本を読みたがる女の子がいるなんて思っていなかった。おしゃべりの苦手な僕は、彼女とあまり話した事はなかったが親近感を感じていた。同じ物語を彼女と共有していると思うと、彼女の事を知っているような気分になった。おそらく彼女も夢中でページをめくりながら、探偵になったり大きな鳥に襲われたり海で遭難したり、無人島で生活したりしてるんだ。
小野さんと転校生の河村さんはすぐ仲良くなった。休み時間も一緒に過ごしていたし、学校帰りの方向も同じだったので、僕とは反対の道を並んで帰る姿をよく見かけた。僕はというと、コージや陽介や近所の子達数人のいつものメンバーだ。ジャンケンをして負けるとみんなのランドセルを持たされることがあった。小さな僕には苦痛なんだ。持ちきれず引きずるとコージの奴が眼で威嚇するんだ。仲間から簡単にいちぬけたと言えず、ジャンケンに勝っても負けても嫌な遊びだなと思っていた。教室でも授業が終わってからも、みんなと一緒だとひとりだけ別行動をとる訳にいかなかった。コージの気まぐれは誰もが黙認していたのでひとりでさっさと帰る事もあったが、僕にはこんな自由がなかった。
夏のある日、僕らは神社の裏山の道を通って帰った。いつもはあまり通らない道だが、きょうは特別なコースだ。そこの道端には薮に囲まれたスイカ畑があった。小高い山の一部が開けていて狭い畑があったのだ。スイカ畑は無防備で、背の高いひまわりが数本と、隙間だらけの低い竹の柵が申し訳程度にあっただけだった。畑の持ち主は、こんなのどかな町には盗人などいないと信じている素朴な良い人か、全く危機管理のできていない駄目な人だ。僕は前者だと思う。
コージが眼で合図したので、僕は前日下見をして眼を付けていた大きなスイカをもぎ取った。スイカの下には痛まないように藁が敷いてあった。コージも僕と同じ事をした。見張り役の他の三人は、僕とコージのランドセルを持って十メートル先を山の上に向って走っていた。スイカはずっしり重く、慌てていたので何度も草むらに脚を取られ落としそうになった。脚の悪い陽介は邪魔だとコージが言うので、きょうは誘わなかった。気の進まない僕はあの時陽介と一緒に帰りたかったが、やはり、いちぬけたとは言えなかった。
山の上で大きな石の上に立派なふたつのスイカを並べてみた。悪い事をしたという罪悪感より達成感の方が大きかった。だから一番の目的は、スイカを食べる事より盗む事だったのだと思った。僕らは真っ赤な水気たっぷりの甘いスイカを黙々と食べた。山の風は涼しく心地良く吹き渡り、小さな盗人達には優し過ぎた。見おろす田んぼの向こうには町のシンボルでもある大きな川の流れが止まって見えていた。時間も止まっていた。僕はこのままこの町で、ずっとこんな状態で過ごすのだろう。たぶん父のようにこの地で土をいじりながら生きるのだろう。僕には自分の未来なんて何も見えていなかった。大きくなったら何になりたいかという質問に、即答で具体的に答えてる奴なんて信じられなかった。お医者さんとかバスの運転手とか先生とか、大人の期待に応えて演じてるようにしか見えなかった。心躍らせる危険で華やかな冒険は本の中にしかなかった。あるいは、それらは空想癖の僕の頭にしかなかったし、現実では起こりえない事だと知っていた。シンドバッドでもガリバーでもない現実の僕の冒険は、せいぜいスイカを盗むくらいが関の山なんだ。僕は最後の甘いかけらを味わって、小さな満足の溜め息をついた。そしてスイカの皮を思い切り青い空に放り投げた。
昼休みに図書館で河村さんが本を読んでいた。珍しく小野さんはいなくてひとりだった。ピアノが得意だというあの自己紹介がずっと頭に残っていた。きっとお金持ちのお嬢さんで、自分とは随分かけ離れた生活をしているのだろう。朝僕は顔を合わせると挨拶はしたが話した事はなかった。彼女の周りはいつも華やいでいるように見えたから近づき難かった。目立ちたがりの園田は、彼女が転校して来たその日から調子良く話し掛けていた。コージは興味無さそうで、陽介は僕と同じように遠くから眺めていた。森君はクラスの事や学校の事を教えてやった。大柄な森君は同級生というより先生に近いなと陽介が言った事があった。気配りが出来て面倒見も良かったから、確かに頼れる存在ではあった。絵もうまかった。真面目一辺倒ではなかったから、皮肉たっぷりな先生の似顔絵をこっそり見せてくれたりもした。僕も似顔絵に挑戦してみたが、自信がなかったので陽介にだけ見せてやった。ノートの端っこに描いた先生の似顔絵を見て奴は、怒った猿みたいだと言った。怒った猿はすぐ消しゴムで消される運命だった。でもそれ以来先生が怒る時、僕は猿を思い出すようになってしまった。しばらく笑いをこらえるのに困った。
昼休みが終わったので図書館から出た。僕は河村さんの後から教室に戻った。園田が僕に近寄って来て、僕と河村さんを品定めするように見た。一緒だったんだねと園田は僕に言って自分の席に戻って行った。変な奴だ。僕は園田があまり好きではなかった。でもあいつは妙に人なつっこくて憎めなかった。絡みたくないと思ってる僕を校庭に引っ張り出しては相撲をとりたがった。チャンバラもドッジボールも鬼ごっこも、園田が強引に誘わなければいつも僕はぽつんと遠くで見ているだけだったかもしれない。何にでもちょっかいを出すあいつを鬱陶しいと思いながらも、僕はどこかで感謝もしていたのだ。
河村さんは他所からきた転校生という身分から抜け出し、もうすっかりクラスに馴染んでいた。最初は何処に行くにも保護者のような小野さんにくっ付いていたが、今は巣立ちの鳥のようにひとりで行動できるようになった。クラスのお客さんという立場をすでに卒業していたのだ。おとなしいと思っていたが活発な明るい子だというのも解ってきた。運動場の片隅の草むらでバッタを追いかけていたかと思うと、近くの椎の木によじ登ったり、数人の女の子達に混じって賑やかにゴム跳びなどもしていた。
ある日、河村さんはあまり女の子は行きたがらない講堂の横の池に行った。彼女の好奇心は強かったしすぐ行動にも移した。コージと同じように蛙やトカゲをあっさり捕まえたので、そんなのお嬢さんのする事じゃないよと僕は驚きつつ呆れた。彼女は愛おしいものを見るように手のひらにトカゲを乗せて、家に持って帰りたいと言った。
五時間目の授業は算数だった。僕は苦手だった。並んでいる数字を見るだけで憂鬱で頭が痛くなった。掛け算の九九が暗唱出来なくて居残りをさせられたくらいだ。時間をかけてやっと掛け算の方法は理解出来たが、割り算なんて到底意味が解らなかった。先生は掛け算が理解できれば割り算もできる筈だと簡単に言うけど、僕は混乱していた。僕にはこんなややこしい事を解決する脳みそが備わっていないんだ。優秀な森君の半分も僕の脳は働いてくれない。陽介やコージも得意ではなかったが、僕よりはマシだった。算数が無くて好きな本だけ読んでいられる学校があれば、僕はすぐにでも転校する。算数の時間になるといつも教室から逃げ出す自分を想像した。
僕はうつむき加減で授業を受けていた。何やら机の脚の下で動いているのが見えた。左前方だ。まだ誰も気づいていないがトカゲだ。たぶん河村さんの机の中から逃げ出してきたのだ。さっき池で捕まえた奴だ。先生に見つかるときっと怒られる。河村さんが怒られるのは可愛そうだと思った。僕はトカゲなんて苦手だったが、こっちに来たら捕まえて隠してやろうと覚悟を決めた。トカゲはちょろちょろと動いたが、こんなところに自分の居場所などある筈もなかった。先生は黒板に向って僕には理解不能な数式を書いていた。トカゲは河村さんの席の近くまで戻っていた。何人かが気づいて指差した。先生が振り向こうとした時、河村さんが足でトカゲを踏んづけた。そのままゆっくり引き寄せて鉛筆でも拾うようにそっと捕まえた。僕はほっとした。でも捕まえたトカゲを河村さんに渡して感謝されるという妄想はあっけなく消えた。僕の精一杯の勇気は試される機会を失った。授業が終わった。黒板に書かれた夥しい数字の羅列が消され、僕の空想も小さな勇気も同時に消えた。
雨は壊れたシャワーのようにいつまでも降り続いた。空と大地は雨で連結されてひとつになった。小さな水たまりはいつしか池のようになり、湖のようになった。地鳴りのような鈍い音を響かせて、濁流は山肌を深く傷をつけながら駆け下りた。水に弱いシラス台地は情け容赦ない大量の雨に浸食された。町を取り囲むように切り立った崖も、水をたらふく飲まされていた。ついに我慢の限界に来た崖は、海辺の砂で作ったお城のように崩れ、電柱をなぎ倒し家を押しつぶし道を塞ぎ、僕らの気分を滅入らせた。
おとといの夜から降り始めた雨が、今朝は一段と強くなった。傘をさしても大粒の雨に穴をあけられそうな勢いだった。道はというと、道とは名ばかりで人の流れはなく水の流れになった。特に僕らの集落のある山際の坂道は急流になり、大きい木の枝や石を巻き込んで流れた。風も山の木々をなぎ倒すように荒れ狂い、枝と枝は擦れ合い傷つけ合った。高波の押し寄せる港の船は引き上げられていたが、波は防波堤やテトラポッドを軽々と乗り越え船を引き戻そうとした。
海辺には潮風で錆びたトタン屋根の小屋がいくつかあった。時々僕らはその周りで、かくれんぼや缶蹴りをして遊んだ。そこには網や釣りの道具が入れてあったが、そのひとつは波にさらわれ一瞬にして消えた。台風銀座の先端にある僕らの町は、いかにもその名に恥じない状況で、当然のように学校は休みになった。小学生の僕らが外に出かけるのは、嵐の海に小舟で漕ぎ出すようなものだった。
夕方になったが、どの家にも明かりは点かなかった。やはり停電だ。ロウソクをちゃぶ台の真ん中に立て、すきま風に震える明かりの中で味気ない夕食が終わった。台風は直撃していた。家は木製の船底のようにぎしっぎしっと揺れて暗い不安をかき立て、僕は泣きそうになりながら耐えた。屋根を剥ぎ取ろうとする風が波のようにしつこく繰り返し襲ってきたが、じっと耐えてやり過ごすしかないのだ。父は家の周りに大きな丸太のつっかい棒を何本も立てたが、強風の前ではその努力もむなしく感じた。日頃は何でも知っていて何でも解決出来る父も、台風の破壊力に対しては気休め程度のつっかい棒が精一杯だった。夜なのに寝るわけにもいかなかった。雨戸や屋根が飛ばされたら避難しなければならないからだ。まんじりともしないで夜をやり過ごすしかないのだ。こんな暗い中で長時間不吉な音を聞かされると、悪い方向へだけ想像力が働くものだ。猛威をふるう自然の前で無力な僕らは、寄り添っているだけであまり話す事がなかった。だから余計に不安な気分の中に閉じ込められてしまっていた。
僕はいつの間にか眠ってしまったらしい。朝いつものように目覚めたのはいつもの布団の中だった。雨も風の唸りも止んでいて山里の静けさが戻っていた。家はどうやら無事で僕らを守ってくれたのだ。朝とはいえ停電で暗い中、母はご飯の準備をしていて父は外の様子を見に出ていた。たぶん田んぼの稲の事が気がかりなんだ。僕も外に出てみた。庭中木の葉が散らかっていた。春に母は庭の日当たりの良い所にダリアの球根を植えた。そのダリアは、貧しい家には不似合いな程の赤い華やかな大輪の花を咲かせていた。だが今は見る影もなく泥だらけで地面に這いつくばっていた。台風一過の空はまぶしくて、ゆうべ怯えて泣きそうになっていた僕をからかっているようだった。
家のすぐ下を流れる川は水かさが三倍にも増えて、岩の間から流れ落ちる小さな滝はダムの放流を思わせた。僕は心配になった。ここに住んでいた小さなエビやハゼや蟹達は、こんなに激しい流れに逆うなんてできないだろう。ずっと下流まで、もしかしたら海まで押し流されて、もう戻って来れないかもしれない。
小魚達が濁流にもみくちゃにされ、岩や岸にぶつかり粉々に砕ける姿を想像すると、悲しいような落胆した気分になった。
学校では先生に注意された。台風が去ったとはいえ、崖の近くや川には近づかないようにと念を押された。陽介と僕は学校帰りに台風の被害をあちこち視察した。直接我が身に危害を及ぼす台風は怖かったが、去った後はちょっと興奮して歩いたものだった。見慣れた風景が一変しているのは驚きだった。陽介は脚が悪くて左足を引きずるように歩いたから、僕はそれに合わせてゆっくり歩いた。脚のせいなのか、陽介は名前と裏腹に暗い感じのする子だ。笑う時はにっと口元を引きつらせるように笑い、顔全体でにこにこ笑ったのを見た事がなかった。普段は静かで優しい彼の父親は酒癖が悪くて、陽介の脚が悪いのは父親の暴力に原因があったらしい。さすがにそんなことを陽介本人に確かめた事はないが、父親が暴れ出すと、夜中でも近所の親戚の家に避難するんだとこぼした事があった。でも陽介は父親を嫌っているようには見えなかった。庭で一緒に薪割りをしたり、自転車の練習をしたりキャッチボールをしている事もあった。僕はそんなふうに父と遊ぶ事なんてなかったから、羨ましかったくらいだ。
僕らは映画館を右に見ながら橋の上までやって来た。映画館の看板が無くなっているのは遠くからでもすぐ気づいた。大量の濁った水が河川敷を飲み込んで川幅は倍になっていた。僕らは飽きもせず上流から流れて来るものを見ていた。製材所にあるような大きな丸太や切り株や大小の板きれ。屋根の一部や窓枠や机や、鍋やヤカンや電球や犬の死骸まであった。二本のガラス瓶が口を水の上に出して立ったまま流れて来た。焼酎の一升瓶のようだ。瓶が付かず離れず並んで流れて行くのを指差しながら、あれはきっと双子なんだね、陽介がにっと笑って言った。台風の惨状を示す痛々しい証拠物件が、今まさに僕らの下を流れている。無責任な傍観者の僕は、陽介の真似をしてにっと笑った。
僕らは町はずれまで来た。僕の家はまだ遠いが陽介の家はもうすぐだ。神社の境内の大きな楠が、上の方を三分の一折られて吹き飛ばされていた。ぷつんといきなり上が無くなっている姿は、図書館で見たバオバブの木に似ていた。境内の横にある梨の木は無事だった。だが実りの季節まであとわずかだというのに、すっかり実を落とされてしまった。僕らは大きそうな実を選んだ。ズボンの膝で泥を拭いてかぶりついた。固くて食べられるのはわずかだったが何個かは甘いのがあった。台風の奴はひどい事ばかりする。でも、こんなおやつもくれる。
山の集落へ向う途中コージの家が見えて来た。小屋のトタン屋根が無くなっていた。様々な工具が野ざらしで恥ずかしげに見えた。相変わらずラジオからは歌謡曲が流れていたが、いつもと様子が違う。大人達が数人集まっていた。腕組みしながら何やら相談しているようだった。コージはポケットに手を突っ込んでタイヤをこんこん蹴っていた。大雨で緩んだ裏山から大きな岩が転がり落ちて来たのだ。かろうじて家のすぐ脇で止まっていた。転がって来た跡がくっきり地面に印されていた。子供が四五人は乗れそうな大きさで、泥付きで、木や草の根っこ付きの岩だ。積み重なった大量の古いタイヤが無かったら家は潰されていただろう。粗大ゴミの邪魔者と見なされていた古いタイヤが一家の危機を救ったのだ。
陽介は小声で言った。コージの奴が岩の下敷きになっていたら、もう殴られずにすんだのにね。冗談ではなくて真顔だった。だから........僕の方がにっと笑ってやった。
朝の意地悪な風が、校長先生の薄くなりかけた髪をゆっくりめくるように逆立てていた。先生は後ろに組んだ手を離して、髪を直そうかどうしようか一瞬迷った素振りをしたが、そのまま話を続けた。ちょっと鬱陶しいと感じている表情が額のシワをさらに深くした。白いものがちょっと混じりかけた髭は、校長としての威厳を無理矢理保とうしている風情だった。朝礼台は小さな僕の前に立ちはだかり、僕は少々疲れていた。朝礼の時の先生の話は毎日同じようなものだったからだ。朝礼の時気分が悪くなって倒れる子がいたが、あれは弱い子にできる精一杯の抗議なんだ。朝礼の時には、手を洗いなさい、風呂に入りなさいと言われ、ハンカチを持ちなさいと言われ、挨拶や歯磨きの仕方を習い、軍隊のように規律正しく列に真っすぐ並ぶことを習った。社会性のない僕らは、このように躾けられ飼いならされるべき小さな獣だった。
標準語も習った。教頭先生の後に続いて、小さな僕らの千個の口が同じ言葉を繰り返した。先生という親鳥から餌を貰うひなのように、僕らは口をぱくぱく大きく開けた。団塊の世代より数年遅れの僕らの世代も、子供達はまだまだ多かった。田舎の小学校にも子供達があふれていた。教頭先生は「が」という言葉のとき独特の鼻に掛かった発音をした。「私が」と言う時、僕には「私んが」と聞こえた。教科書は当然標準語で書かれていたから、僕は文字としての標準語に抵抗はなかった。でも標準語で話すのはどうだろう。コージの事を思ったらおかしかった。あの乱暴者のコージまでがお上品な標準語だなんて、似合うわけないじゃないか。
朝礼の時間がいつもより長く感じられた。きょうは映画教室の日なんだ。授業は途中で終わりだ。先生に先導されながら、僕らは二列になって賑やかに映画館に向った。校門の前の文房具屋のおばさんは、僕ら全員の顔を知っていた。学校で必要な物はみんながここで買っていたからだ。消しゴムや鉛筆削りやノートを万引きした子の顔も列の中にはいくつかあったが、いつもと違うちょっと興奮気味の僕らの顔をひとりひとり見送りながら、にこやかに手を振った。町の役場や警察署の前を通り消毒液の匂う病院の前を抜け、同級生の母親が切り盛りする雑貨屋の前まで来ると橋の欄干が見えてきた。映画館は川の近くにあった。
川は僕らの町をふたつに分けて流れていた。だから川北とか川南とか呼ぶ地名がある。海の近くは潮入りと呼ばれ、昔お城の在った地域は城内と呼ばれ、僕の住む山の方は山本と呼ばれた。この頃の川は生活排水や山の開発などの影響も目立つ程ではなかった。家庭から出る茶碗や長靴や電化製品などのゴミが、川底に無様に沈んでいることもなかった。僕らは学校帰りに橋の上から身を乗り出して、流れに揺れる水草や石の間を泳ぐ鮎を眺めた。夏の暑い日などは、涼しげに澄んだ水の中の、あの鮎になりたいと思った。
映画館は木造の学校の講堂に似ていた。商店街の裏手にあって、錆びた槍のような木立と田んぼと川岸の葦の原に囲まれていた。入り口付近には映画のフィルムの切れ端が落ちていたり、古いポスターが踏みしだかれていたりした。僕らは映画館の後ろの入り口から入った。スクリーンのある前方へ順番に進んで木製の五人掛けの椅子に座った。左前方が非常口で右にトイレがあった。運悪く右端の方に座るはめになるとたまに悪臭が漏れてきた。立て付けが悪くドアもしっかり閉まらなかったし、水洗トイレはまだなかった。冬は大した事ではなかったが、夏はちょっときつかった。でも映画が始まってしまえばトイレの事などすっかり忘れた。
文部省推薦の映画は、例えば、父母のいない兄弟が貧しくてもけなげに生きるというような、愚直な程の感動を誘うものだった。子供というのは愚直な程正義感が強く、そのくせ愚直な程の嘘も平気でつくものだ。つまり、いずれにしてもそれはそれで僕らは素直に受け止めたというわけだ。でも僕らは、何といっても中村錦之助や大川橋蔵が目当てだった。海が映る。岩場で砕ける波が僕らの方に向ってきて、東映の文字がスクリーンに映し出されるとわくわくした。一心太助や番場の忠太郎や宮本武蔵や、若様侍捕物帖や新吾十番勝負に興奮した。錦之助は生きが良くて橋蔵はきりっときれいだった。僕らはメイクというものを知らなかったから、ああいう人だと思い込んでいた。虚構の映画と現実との距離など考えた事もない。僕らはひたすらスターに憧れ、スクリーンに向って拍手をし、興奮のあまり木製の椅子をぎしぎし揺すった。
当時映画はフィルムが途中で切れてしまうことがあった。例えば、悪い代官に捕らえられた娘を助ける為に主人公が駆けつけるシーンで、いきなり映像がぷつんと消えてしまうのだ。そして数分後フイルムが繋ぎ合わされて再び映像が現れると、もう違うシーンへと飛んでしまっている。僕らはあーっと溜め息をもらし、またかと諦めた雰囲気が館内に満ちた。悔しいが珍しい事ではない。不満そうに映写室をいっせいに振り返るが、誰も文句は言わなかった。不幸に慣れるという事はこういうことなのだ。不平や不満があっても、周辺や自分自身にも満ちてくる諦めの気分にじんわりと押しつぶされるのだ。
映画が終わっても興奮覚めやらず、椅子の上でずっと余韻に浸っていたかった。でもいつも先生にせかされた。しぶしぶ映画館を出ると、いつものように川は流れていて、いつものように変わり映えのしない町の風景があり、いつもの教室が待っていた。スクリーンの中には侍が沢山いて、雨の中で刀を振り回していたのに、映画館を出るとまぶしい太陽があり、見慣れたおじさんやおばさんが世間話をしていて、僕は映画と日常との落差に目眩がするほどの脱力感を感じた。
僕らは、この代り映えのしない退屈な日常に対抗すべくチャンバラごっこをした。乱暴なコージも優等生の森君も運動神経抜群で目立ちたがりの園田も、おとなしい僕もみんなが好きだった。みんなが錦之助や橋蔵のような良い役をやりたがった。たまに悪役と正義の味方に別れたりしたが、当然、自分からすすんで悪役になる子はいなかった。そこで森君の意見を尊重して悪も正義もなく、ただ敵味方二手に分かれて戦った。園田はどこで練習したのかバク転ができた。忍者の役にはぴったりだ。僕があれをやったら突き指ではすまなくて、たぶん首の骨を折ってしまうだろう。園田は滅多に切られる事はなかったが、切られる時は映画のシーンみたいに派手に上手に倒れた。あんな風に倒れられると切る側もかっこ良く見えた。
掃除の時間だった。教室の隅でちいさなチャンバラが始まった。ほうきやハタキでふざけ合っていたのが、いつの間にか興奮が伝染して僕まで巻き込まれてしまった。何事もそうだ。僕は台風の目になるようなタイプではなかった。いつも受け身で巻き込まれる側だ。女の子達は、困ったいたずらっ子を見る母親のような眼で見ていた。呆れていたひとりが大きな声で静まるように注意したが、そんなことでは終わらない。突然ガチャンと音がして窓ガラスが砕け、教室の中にも外にも破片が飛び散った。ちっぽけな侍達は、刀ではなく危うくガラスで斬られてしまうところだった。僕らの興奮は一気に醒めた。白々しい空気がみんなの隙間を走り机の中まで浸透した。
担任の先生には当然のことながら怒られた。珍しく森君が先生に抗議した。ずっと以前に女子がガラスを割った事があった。その時先生は怒らずに、まずケガが無かった事を喜んだ。森君の言うには、なぜ女子の場合は怒らずに男子が割ると怒るのかというものだった。僕は黙っていたが、森君、それは通らない主張だよと思っていた。女子はたまたま掃除中にうっかり割ってしまっただけで、チャンバラで騒いでほうきで割ったのとは訳が違う。他の男子は、そんなのえこひいきだと無邪気に森君に賛同した。また興奮が伝染しそうだったが、僕はついていけなかった。抗議の声を上げない僕を見て園田がせせら笑うように言った。お前は先生のお気に入りだからな。
ガラスの事なんか僕の頭から抜けてしまった。僕はひとり別の世界にいる気分だった。そうなんだ。この事に関しては先生は何も解っちゃいないんだ。先生のお気に入りってことは生徒達、仲間にとっては気に入らない奴の事なんだ。僕は教室で居心地が悪いんだ。だから先生、コージが誰かを殴っても、おとなしい僕と比べないで欲しいんだ。僕が図書館で本を沢山読んでいるなんて、みんなの前でわざわざ言わないで欲しいんだ。校庭に落ちていた百円玉を僕が先生に届けた事も、正直者の見本みたいにみんなに発表しないで欲しい。先生、お願いだから.......何かにつけて僕を引き合いに出さないで欲しいんだ。
すり減ったブーメランのような月が製材所の上に出ていた。どこまでも青い空を背景に、雲は火の見やぐらをかすめる程に低空飛行しながら、海からの強い風に流されて様々に形を変えていった。僕は雲の形に飽きることがなく首が疲れてしまうまで見上げていた。大きな口を開けたワニが、数秒後には左に流されて太ったガマガエルになり、ロケットになり、寝ているおじいちゃんのようにもなった。それはまたすぐ別の雲と合流して、まるで操縦不能の出来そこないの鉄人28号のように飛んで行った。
学校帰りに僕とコージは製材所に立ち寄った。まだ樹皮の付いた大きな丸太の上に座った。僕らの背丈の数倍もの高さに、太い丸い木が何本も無造作に積み上げてあった。近くの神社の鳥居よりずっと太い木が、向こうの田んぼの近くまでずらりと横たわっているのだ。時々数人で木から木へと飛び移り、多少危険な鬼ごっこをした。木がいつ転がり落ちてくるかも知れず、大人に見つかると叱られた。道端や校庭での追いかけっこより変化があってスリルがあったのだ。ここで遊んで帰ると、運動靴の中には必ずおがくずが入っていた。
製材所のおじさんはタオルを頭に巻いて、大きな丸い電気ノコで角材を切り出していた。僕は鼻の奥から頭の芯まで浄化するような刺激的な木の匂いも、木を切るキーンという甲高い音も好きだったので、おじさんに見つからないようにしながら学校帰りにいつもここで道草を食った。僕とコージは、二人で半分ずつ出し合って買ったキャラメルを口にしながら、オマケの自動車を吟味していた。走れるように車輪はちゃんと回ったが、黄色いちっぽけなバスだった。僕は飛行機が欲しかったので、車は気前良くコージに譲った。そう言うと格好はいいが、実はオマケが何であろうと結局は全てコージの手に入ることになっていた。
コージは実に乱暴な性格で両親も先生も手を焼いていた。ランドセルに隠れてしまうような小さな僕より、さらに小さな身体のくせに、その全身には攻撃的な力をいつでも発揮できる態勢が整っていた。言葉と行動の間に何のクッションも無く、鉛筆でお前の手を刺してやる、と言ったらその通りにするような奴だ。砂場で喧嘩をして相手に馬乗りになって、眼に砂を擦り込むようなそんな奴だ。小学校での初めての父兄参観日だった。国語の授業中に、僕は丸めた教科書でいきなり後頭部を殴られた。コージの落とした消しゴムが、前の席の僕の足元に落ちた。拾えよ。奴は言った。
教室の後ろの壁には、目をつぶってクレヨンで描きなぐったような僕らの絵と、「ろ」と「ら」の区別もつかないような字で書いた作文が画鋲で留められていた。いつもと違って校長先生や母親達がいっぱいいて、担任の先生もいつもより笑顔が多くて、僕はすっかり緊張していた。拾えよ。奴は言った。僕は大勢の視線の中でヘタな動きをしたくなかった。おそらく母も、僕のことを気にしながら授業を見ているに違いない。もじもじしているといきなり右の後頭部にバシッ。教科書は本来の使用法ではない武器として使われたのだ。こんな奴だったがコージはいじめっ子ではなかった。特定の子を狙うことはなく、自分でも解らないエネルギーを持て余すかのように、いつでも誰に対しても粗野で乱暴だったのだ。親も先生も同級生も彼にとって細かい区別などなかった。
僕らは帰る方向が途中まで一緒だった。コージの家は町から山へ向う坂の登り口にあったが、山の方まで帰る僕よりずっと町の子だった。父親は自動車の修理をやっていた。家の周りには古いタイヤが、見捨てられた憂鬱な記念碑のように積み重なっていた。夏になると全てのタイヤに雨水が溜まり、大量のボウフラを飼育した。トタン屋根の即席の小屋にも車の部品や工具が雑然と置かれていた。農家の僕のうちには無いペンチやドライバーやジャッキや、歯車やねじやゴムの端切や、名前も知らない道具が珍しかった。商売繁盛とはなかなかいかないようだった。当時僕らの町に車は少なく、町のど真ん中でさえ信号なんて必要なかった。父親もタイヤも部品も工具類も、そして家の周りの風景までも客を待ちわびて退屈していた。
退屈を紛らわすためかラジオが付けっぱなしで、歌謡曲がよく流れていた。三橋美智也の「哀愁列車」や「夕焼けとんび」が流れ、島倉千代子の「からたち日記」も聞こえていた。美空ひばりの歌もよく聞いたが、僕は島倉千代子の方が好きだった。顔など知らなかったが声を聞いて、可憐な可愛い女性だろうと勝手に思い込んでいた。子供の頃は意味など解らなくてもすぐ歌詞を憶えて歌ったものだ。僕らにとっては、国歌も校歌も学校唱歌も、まるで意味の解らない言葉だらけだった。世界は謎の言葉であふれかえっていた。
小学校の校庭の右端には木造の講堂があった。入学式や卒業式や学芸会などが行われ、雨の日は朝礼もここでやることがあった。たまに大道芸人みたいな人が舞台に立つこともあった。頭で瓦を次々と割ったり、手で刀をぐっと握ったまま引き抜くなど怖い荒技も見せた。学校にわざわざ呼んで見せるような、「教育上好ましい」人達ではなかったと思うが、多分先生達もこの町では余興に飢えていたのだ。講堂の隣には池があって、二宮金次郎が薪を背負って本を読みながら池の方を向いて立っていた。僕らも金次郎のように本を読みながら道を歩くことがあったが、危ないというので先生に止めるように言われた。だから金次郎のような偉い人にはなり損ねてしまった。池の後ろは山で、せり出した大きな岩が池の三分の一を占めていた。池の周りは紫陽花などの低木が生い茂り、南国らしくバナナの木もあった。パン屑を投げてやると、緋色の鯉は非常時の潜水艦のように泳いで集まった。時々、ただのゴミを投げてはからかってやった。亀は自身の性格に従い岩の上をのそのそ這って甲羅を干した。浅瀬のおたまじゃくしはかわいい尻尾を振って緑の藻とじゃれていた。
ある日の昼休み、僕らは数人で池の周りで遊んでいた。蛙を捕まえたり、意味も無く泥を棒で突き回したり、岩の上に這い上がったりしていた。ひとり何処かへ消えていたコージが、なにやら紐のようなものをぶら下げて薮の中から出てきた。1メートルちょっとはありそうな青大将だった。僕は田舎で育ったくせに爬虫類が苦手だ。蛇なんて見たくもないし近寄りたくもない。おたまじゃくしや蛙ならなんとか触ることができるが、好んで触ろうとは思いもしない。情けないことにトカゲにもイモリにも触れない。特にイモリは見るだけでも嫌だった。黒い体かと思っていると、腹側は予想を裏切る毒々しい赤なのだ。あの配色は間違っている。
コージには持論があった。蛇の尻尾を持って頭の上で振り回す。右回りだと蛇は平気だが、左回りだと弱って死んでしまうというものだった。以前にもコージは試したことがあった。木の葉とか紙くずなどの家のゴミを始末するために、道端で焚き火をしていた時だった。この時も捕まえた青大将で試したが、何回やっても蛇は死んだりしなかった。こんな手ひどい拷問を受けたのだから弱ってしまうのは当然だと思ったが、蛇は平気だった。コージが道に降ろしてやる度に、何事も無かったかのようにスルスルと地面を滑って逃げようとした。コージは苛立を隠さない眼で、焚き火の中に蛇を持って行った。熱さに身をくねらせる蛇のウロコがじりじり焦げて、思わず僕は眼を逸らせた。魚を焼くような意外に香ばしい匂いがした。この時魚売りのおばさんが通りかかっても、まさか蛇を焼いているとは思わなかったに違いない。
池の砂地でコージはまたあの時のように蛇を振り回し始めた。僕には結果が解っていたが、他の子達は新種の宗教儀式を見るように聖なる回転を眺めた。蛇は柔らかにしなりながらびゅんびゅん唸って回った。こんなに回されるとウロコが一枚また一枚と剥がれていくのを想像した。ウロコははらはらと僕の頭上を舞い、首筋から服の中にまで忍び込むだろう。そして肌にぴったり張り付いて取れなくなり、僕の身体は蛇の匂いに包まれる。僕は身震いをして後ずさった。
講堂に向って音楽の先生が歩いていた。茶色の大きな封筒と本を抱えていた。先生は僕の母と同じくらい年老いた女の人だった。白髪は染めていたので生え際だけが少し白く、あまり目立たなかった。髪は頭のてっぺんで団子のように丸めていた。ピアノやオルガンを弾く時、団子は揺れて転がり落ちそうに見えることがあった。先生は細い眼鏡を右の親指と人差し指でせわしなく持ち上げるのが癖だった。いつものように眼鏡に手をやって講堂の入り口に立った。その時、不気味な衝撃とともにいきなり先生の首にひんやりした重い紐が巻き付いた。それは池のバナナの木の辺りから飛んできた。講堂の重くて厚いドアをも揺さぶるような悲鳴が聞こえた。僕らは先生が腰を抜かしている隙に、池の脇の図書館の裏に駆け込み何事もなかったように教室に戻った。勢い良く振り回していた青大将からコージの奴が手を滑らせてしまったんだ。僕には何の責任も無い。でも奴が自分から白状しない限り、僕らは誰にもこのことをバラしちゃいけないんだ。
風呂上がりにベランダで涼みながら、大きなマンションやアパートの明かりを眺めることがある。あのひとつひとつの明かりの中にそれぞれの生活があり、その家族のひとりひとりに様々な人生があり、様々な日々のエピソードの集積があれらの部屋に満ちているのだろう。そして、生きる事はエピソードの連続だと思いながら、僕と同じように、向こうのベランダからこちらの部屋の明かりを眺めている人がいるかもしれない。
夜になると深い闇が僕らの集落を隅々まで覆った。山も川も田畑も防空壕もマムシのいる山道も、そして時計草の白い花までも漆黒に沈んだ。星も月も出ない夜、一歩外に足を踏み出すと闇の世界に圧倒されたものだ。しかし不安と同時にその世界に慣れてくると、妙な安堵感があったような気もする。距離感どころか空間もなく時間さえ無いようなひたすらの闇。僕は闇の中で眼を閉じたり開けたりしてみた。いずれにしても闇があるばかりだ。眼の見えない人っていつもこんな世界にいるのか。幼い僕はそんな事を思いながら、こんな闇の世界でも生きていける人ってなんてすごいんだろう思った。
星も月も出ない夜。ほろ酔いの大工のおじさんが、提灯を持って家に向っていた。僕の幼い頃、提灯はまだ必需品だったし、ロウソクも大きな箱入りのマッチもどこの家でも常備していた。玄関の修理を頼まれたおじさんは仕事を終えると、その家でさつま揚げと芋焼酎をごちそうになった。嫌いではないのですすめられるままつい飲み過ぎてしまった。さつま揚げを僕らは「ちきあげ」と呼んだ。母も作ったが、あまり上等の魚は使わなかったと思う。港の方から天秤棒を担いだおばさんが、魚はいらんかねと売りにきた。たまにおばさんはうちの縁側でお昼の弁当を食べた。母はお茶を出してやって世間話の相手をした。おばさんの魚は獲れたての新鮮なものだった。ちきあげを作るには、まず鯵とか鰯の地魚をすり鉢ですりつぶすのだが、小骨が少しあるくらいがおいしかった。すり身には豆腐も入れるのでふっくらになる。塩を入れ、そして砂糖多めで甘めに仕上げた。これが芋焼酎のお湯割りによく合うのだ。
おじさんはまっすぐ歩けないので、提灯をゆらゆらさせながらゆるい坂道を下って来た。小さな滝のある川の所に出た。川の土手は小さな竹やぶになっていた。タケノコの季節になると、僕らは競い合って細くて柔らかいタケノコを取ったものだった。おじさんは竹やぶに向っておしっこをしようとして、大工道具と提灯を下に降ろした。降ろしたと同時に風がろうそくの火を吹き消し、突然の闇におじさんはふらつき川に滑り落ちた。幸い砂場に落ちたので、ズボンが膝の辺りまで濡れただけでケガはなかった。しかし何の手がかりも無い闇の中では、どこから這い上がっていいものやら見当もつかない。闇の中で溺れている人のように手を動かしてはみたものの、すぐ無駄な事だと諦めた。酔っていたので、しばらくすると滝の音より大きないびきをかいて寝込んでしまった。
朝早く、近所の迷信深い婆さんが川下から歩いてきた。畑に野菜を取りに行く途中だったが、向こうの竹やぶが怪しく揺れているので立ち止まった。曲がった腰を伸ばして、もんぺの腰に手を当てた。見てみると川から河童が這い上がってくるところだった。婆さんは竹で編んだ籠を胸に抱えたまま、ヨモギの草むらにお尻から座り込んだ。大工道具を肩に、その河童はゆっくり近づいてきて照れくさそうに挨拶した。河童の存在を信じていた婆さんは、人なつっこいおじさんの笑顔を見てもしばらくは疑わしそうな目をしていたらしい。ずっと後で聞いた話だが、下流に住んでいたおじさんは奥さんに言われたそうだ。せっかく川に落ちたのだから、そのまま流されてくればうちに着いたのに。
僕の幼い頃は、生まれるのも死んでいくのも病院ではなく自分の家だった。田んぼで働いている時に出産した話を聞いた事もあったが、とにかく生と死はすぐ傍らにあった。僕はある葬列を思い出す。彼女の名は仮にユキとしておこう。彼女の棺桶は大きな水瓶だった。水瓶は縄で縛ってあって、二人の男達が丸太ん棒の前後を担いだ。苔むした石段をそれはゆっくり揺れながら降りてきた。石段の両側にはみかんやつつじの木が植えられて、草花もよく手入れされていた。
当時、まだ僕らの集落では土葬が当たり前だった。普通は四角い縦長の木の棺桶が使われた。亡くなった人は膝を抱えるような前屈の姿勢で中に入れられ、集落のはずれのお墓まで担がれて行った。竹竿に付けた旗を持った行列が棺桶に続いた。石ころだらけの不安定な道を行列は静かに進んだが、死というものを理解していない幼い子供達は、行列から外れてふざけあったり甲高い声で笑ったりした。
なぜユキの棺桶は普通の木製ではなかったのだろう。普通の人ではなかったユキの為の特製の棺桶。その中もただひたすらの闇だったのだろう。ユキは学校に行っている頃は優秀な生徒だったらしい。そんな話を聞いて、あまりに頭が良過ぎると狂ってしまう事があるんだと、幼い僕らは真顔で話したものだ。僕はユキの顔を憶えていない。みかんの木の下に佇んでいる姿だけが浮かんでくる。実際に見たものか、誰かの話を聞いて僕が作り出した像なのかも定かではない。
今だったら病院に入れてもらえるのだろうが、彼女は家の離れにいわば幽閉されていた。閉じ込められた狭い世界で彼女はどんな生活をしていたのだろう。世間とも関われず、自分自身とさえ切り離されてしまったような人....。
母親が服を着せてやっても破ったり脱ぎ捨てたりしたようだ。ある時は、畑の芋を掘っては下の家に向って投げた事もあった。僕は実際見ていないから噂話に過ぎないのだが、幼い僕の好奇心と恐怖心は彼女を特別な存在にした。夕方暗くなるまで遊んでうちに帰る時、ユキのいる筈の家の下の道を通る事があった。
その家は高い石垣の上にあった。僕らの集落は山の懐に抱かれるような位置にあって、平坦な土地ではなかったので石垣の家が多かったのだ。ユキの家の石垣の所には柿や梨の木があって竹林もあったので、道はいっそう暗くなっていた。僕はユキも暗がりも怖かったので、そこまで来ると走って帰ったものだ。途中で振返って見たが、ユキの姿がそこにあったことはなかった。でもいつでも彼女は僕の内ではなにかしら超自然的な、圧倒的な存在として常に在ったのだ。何故亡くなったのか、若かった筈だが何歳だったのかも憶えてはいない。ただ、あの茅葺きの家は物悲しい気分と共にはっきり思い出す事ができる。
僕の幼い頃、父は牛を二頭飼っていた。子牛が生まれて三頭になる時もあった。子牛は大切だった。貴重な現金収入になるのだ。でも子牛が高値で売れるのは嬉しかったが辛くもあった。子牛が売られて行った日、母牛は餌も食べず夜になってもずっと鳴き続けた。声が嗄れて、もうかすれた息しか出ないくらい鳴き続けた。そして、ずっと落ち着かない様子で小屋の中を動き回った。我が子の姿を必死で捜そうとする、涙で濡れた黒い大きな眼を今でも思い出してしまう。
こんな頃、僕は母がいなくなってしまう夢を何回も見た。一緒に歩いていた筈の道の真ん中に、いつの間にか自分だけしかいない。呼んでも呼んでも母は応えてくれず、泣きながら目覚めた。目が覚めると母はいつも横に寝ていて、安心した僕は母の背中にしがみついた。母を捜して泣いていた夢の中の僕は、売られて行った子牛と同じだ。でも僕は一回目覚めるだけで母を取り戻せたが、子牛が何回目覚めてもそれは叶わない事だった。
父は田畑での農作業で牛を使った。僕らの集落には馬は一頭しかいなかった。それは主に山から木を運び出すのに使われていて、たいていの家では牛を飼っていた。牛に引かせる車を馬車と呼んではいたが、正確には馬車は一台しかなかった事になる。馬車にはタイヤが付けられていた。タイヤになる前は木の車輪に鉄の輪をはめたもので、でこぼこ道では乗っていてお尻が痛くなった。山の上の畑から帰る時、僕は母と一緒に崖に添って山道を降りたが、父は馬車で埃っぽい道を下った。たまに父の馬車に乗せてもらうこともあった。草と牛と父の匂いと、車の軋る音と、僕らの集落を見下ろす峠の道からの眺めを思い出す。集落の向こうには、町の中央を蛇行して流れる銀色の川がある。川は鹿児島湾に大量の水を運び、満潮時には逆に海からの魚達を受け入れたから、フグやボラや細長いサヨリが川を上った。夕日を浴びた湾の中のおだやかな波はきらきら光っていた。イカ釣り船の漁り火が見えることもあった。さらに向こう、薩摩半島の開聞岳は優しい三角形のシルエットを見せて、遥か右手の空には桜島の噴煙が見えた。父と僕は黙って馬車に揺られながら、急速に色を失いつつある夕方の風景に同化していった。
囲炉裏の前で焼酎を飲みながら、時々、父は昔住んでいた九州の北の町の話をした。この集落しか知らない僕にとっては、まるで遠い国の話みたいだった。見せてくれたセピア色の写真には背広姿の若い父がいた。一日中田畑で働いている父とは別人で、ますます遠い国の話みたいだと思った。父にも母にも若い頃があって、上の兄弟達は僕の知らない父や母を知っているのだ。僕の知らない遠くの町の生活を知っている。少し酔ってくると、父は会社での事を楽しそうに話す事もあった。部下の若い女性が、仕事中にいつもこっそりあめ玉を口に入れる様子や、上司に教えてもらっていない機械に関する計算を自力で解いて驚かれた話や、研修旅行で大きな街に行った話など。囲炉裏の煙が時々眼にしみたが、僕は物語を聞くように聞いていた。母は黙って、新しい薪を火に入れたり鍋の様子を見ながら聞いていた。囲炉裏の煙は自在鈎や天井だけでなく家中を巡り黒く煤けさせた。火は静かにはじけながら燃えて、無骨な父の手や白髪まじりの母の髪を照らし、そしていつもと変わらぬ質素な僕らの夕食を照らした。
猛暑の日の事だ。道のアスファルトが痛くなるような熱に溶けて泥炭地のようになり、運悪く、その泥炭地に踏み込んだハイヒールの女性は脚を上げる事が出来ない。
猛暑の日の事だ。電柱に留まっていたカラスが熱にやられて地上に落ちる。空を自由に翔るための翼、そんな翼を持つ身にとって、石ころのような落下は恥ずべき醜態に違いない。あの黒装束でじりじり照りつける日差しに耐えるのは、確かに困難ではある。
猛暑の日の事だ。僕らは暑いですねと決められた挨拶を交わす。この暑さを共有しそれを分担することで暑さを軽減できるかのように。喜びは人と共有する事で倍増し、悲しみは分かち合う事で減らせると信じたがっている人のように。
夏はいつも暑かった。僕が生まれたのは戦後7年経った朝鮮戦争のさなかだった。つまり僕の過ごした幼い日々は戦後十数年の事だった。「もはや戦後ではない」と言われた頃だ。クーラーどころか扇風機も知らず、うちわだけで乗り切った夏の暑さ。しかも僕の生まれ育ったのは九州の最南端の小さな町だ。南国の暑さは当たり前だった。それだけではなく幼い頃は、僕の周りは貧しさも当たり前で僕は自分の家の貧しさを知らずにいた。三種の神器ともてはやされたテレビも洗濯機も冷蔵庫もまだ知らなかった。僕のうちに米を貸して下さいって近所の子供が来る事だってあった。両親が不仲でいなくなり、おばあさんと暮らしているその子に母は風呂敷に入れた米を持たせてやる。その子はちょっと恥ずかしそうにお礼を言って帰って行く。自分がその子の立場だったらちゃんとお米を借して下さいと言えるだろうか。人見知りの強い僕はその子を偉いなと思い気の毒にも思った。
お米といえば托鉢の坊さんが来る事もあった。出家の姿ではあるがはっきり言って物乞いをする人達だ。僕らは「勧進どん」と呼んでいた。母は湯のみ一杯の米を胸の前に掛けた袋に入れてやった。当時はまだ防空壕が埋められず残っていた。僕らの土地はシラス台地で雨に脆い筈だが、近所に幾つも残っていたので僕らの遊び場のひとつになっていた。「勧進どん」のひとりが防空壕に寝泊まりしているらしいと噂になったので、友達とこっそり見に行ったことがある。近くの谷川のせせらぎも蝉の声もいつも通りなのに、緊張のせいかやけに大きく聞こえた。石ころだらけの道より一段高いところに防空壕はあって乾いた苔の匂いがした。シダが入り口を隠すように生えていてその間から「勧進どん」の寝ているのが見えた。しばらく見ていたが、ピクリとも動かないので僕は死んでるんだと思い込んだ。祖父の死と重ねていたのかもしれない。
僕の記憶に祖父の顔はない。ただ、いつも寝ていた姿だけがある。祖父は貰い物のあめ玉やお菓子を僕のためにとっておいてくれる。そして僕の名を呼ぶ。おじいちゃんが僕の名を呼ぶ時はいつもおいしいものをくれる時だ。僕はにこにこしながら急いで駆けつける。こんな思い出は僕のものというより母が話してくれたものだ。母の話を聞く度にその情景が刷り込まれて、いつしか僕自身の記憶になっていった。ある朝母がおじいちゃんを起こしに行った。栄養があって体に良いというのでいつも生卵を持って行ったものだ。当時卵は貴重だったのだ。おじいちゃんはいつもの姿で寝ていたが、いつものように生卵を飲む事もなくもう二度と眼を覚まさなかった。「勧進どん」もおじいちゃんみたいに動かないので僕は死んだのだと思い込んだらしい。極端な緊張や思い込みは現実の情報を遮断してしまい、心の中の真実が客観的な真実を飲み込んでしまう。おじいちゃんと「勧進どん」が死んでしまったのは、この時の僕にとっては疑う余地は無かったのだ。怖くなった僕らはうちへの近道である狭い山道を夢中で駆け下りた。隣のおばさんに噛みついて三日間寝込ませた、あの毒蛇のマムシが潜んでいる筈の山道を。
僕らは暑さにも貧しさにも慣れていた。迷信や無知や理不尽なものにも慣れていた。人はある状況に丸ごと包み込まれている時、その自分を包み込んでいるものに疑問を持つ事さえできない。世界はそういうものであり自分もまたそういう存在であり、変われるなどとは夢にも思わない。夕方遅くまで遊んでいた幼い僕たちは、高い石垣の上に住む迷信深い婆さんに、暗くなるまで遊んでいると神隠しに遭うよと言われ、川遊びばかりしていると深い瀬に河童が引きこむよなどと言われ、怖くなってあわてて帰った。外の世界を知らない狭い世界では、こんな科学的な根拠のない話を信じるのも簡単なのだ。迷信と現実との間にある扉は容易に行き来できるようにあらかじめ開かれている。特に幼い僕たちにとって迷信も現実のひとつであるに過ぎない。この婆さんや大人達の言う不可思議な言葉を信じていた頃、まだ僕の世界は山々に囲まれた小さな集落だけだった。母に手を引かれて歩いて行ける範囲がすべての世界だった。
今にして思えば海だってそう遠くはなかったが、僕の知っていたのは山の神様と田の神様だけで、港の突端の小さな島に海の神様が奉ってあるのを知るのはずっと後だった。子供達というのは僕たち以外にもいる。このささやかな集落の外にもいっぱいるんだと知った後の事だ。つまり行動範囲がもう少し広がる小学生になってからのことだ。身体の小さな僕が初めてランドセルを背負って、誇らしげに不安げに歩いた時ランドセルが歩いているみたいだと言われた。今時の親ならデジカメやビデオで晴れの舞台に臨む我が子を撮りまくるところだろうが、「ランドセルが歩いている」僕の入学式の写真は無い。七五三の時の写真はあるのだが、多分、この時写真屋さんは他の立派な身なりの子供達を撮るのに忙し過ぎて、ランドセルに隠れてしまうようなみすぼらしい僕を見過ごしてしまったのだ。
暑さにじわっと締め付けられた僕の頭の中で、記憶の断片がかってに繋ぎ合わされて物語になる。ある複数の出来事が事実と事実であってもつなぎ方では事実の本流から離れてしまい、非常に偏った個人的な物語になる。世界の歴史であろうと個人の歴史であろうと似たようなものだ。書いた者が何者かによって、ひとつの歴史は誇らしげにもなり恨みに満ちたものにもなる。悲劇は喜劇で愚かしさは愛おしさにもなる。幼い頃の記憶をたどる事はおとぎ話にも似てしまう。
遥かに遠ざかる五十年という時間のフィルターを通してみると、もはやあれらの全てに手の届かない懐かしさと切なさとで僕は静かに遠くを見る眼になる。春の小川もメダカの学校も、レンゲや菜の花畑も藁葺きの家もいじめっ子も駄菓子屋のおばさんも、もはやおぼろげな僕の記憶の中にしかないという不思議。畑仕事を終えて夕方帰って来る母の汗と草の混ざったような匂い、夕食前のささやかな愉しみの焼酎を飲む父の、やはり汗と煙草の混ざった匂い。あれほど親密な時を過ごしたのに二人ともいなくなり、残り香のような儚い記憶としてしか今はないという不思議。時を経てさらに鮮やかによみがえる記憶があると人は言うが、それはおそらく事実というより、記憶を物語る事で得られる再生された新たな記憶に違いない。僕は幼い日々を振り返りながら、いつしか記憶の発明をしている気分になる。僕は頭の中で様々な記憶のコラージュを試みる。
本格的な暑さの前触れの時期には蛍がいっぱい舞った。僕の家は玄関から石段を降りるとすぐ小さな川が流れている。昔はそこに大きな一枚岩の橋が架かっていた。川には小さなエビやハゼやウナギや蟹がいて、僕らは食べるためというより遊びで獲った。ハゼ釣りは面白かった。ちゃんとした釣り針を持っていなかったので、針金をきゅっと曲げて釣り針の代わりにした。そしてミミズを付ける。錘の代わりは適当な石ころで間に合わせ、そこらの竹を拾ってきて釣り竿にした。ハゼは実に愛嬌のある顔をしている。驚いたようなまん丸の眼。大きな口。トボケたようなふてぶてしいような顔だ。それがヨシノボリという川ハゼの仲間だというのは、ずっと後になって学校の図書館で知った。川には蛍の幼虫とその餌になるカワニナもいた。水はきれいで流れもそう早くはなかったので住む条件としては良かったのだろう。蛍が飛び交うと外に出て僕はしばし見とれた。それからその美しい光を捕まえたくなって素手で追いかけた。母はそんな僕に言ったものだ。薮の中で光っている蛍に手を出してはいけないよ。蛇の眼も蛍みたいに光る事があるのだからね。
僕は運良く捕まえた数匹をガラスのコップや瓶に入れて手元で愛でた。彼らは幼い僕のためだけに優しく光ってくれた。寝苦しい夜、時々母は蚊帳を吊った。
蚊取り線香では撃退しかねる襲撃をこれなら楽に防げた。僕は蚊帳を吊ってもらうのが好きだった。いつもと違う何かしら濃密な特別な空間ができるからワクワクした。その蚊帳の中に蛍を放した事がある。我ながら素敵なアイデアだった。ガラスのコップや瓶より蛍も自由だし、ずっと僕の近くで光っていてくれる。しばらく母は僕の得意げな様子を見ていたが、やがて蛍を放すように言った。神様の使いだよ。
僕らの集落には娯楽施設など無かった。でも子供達は自然の中で幾らでも遊び方を知っていた。ヒヨドリを捕るためのワナを仕掛けたのもそのなかのひとつだ。弾力のある細めの木と紐と、鳥をおびき寄せるための木の実があればすぐ作れた。紐が無い時はカズラで間に合わせた。ワナを仕掛けた翌日は成果を期待して山に見回りに出かけた。四五カ所のワナのうち大抵は何の変化もなく、たまに哀れな野ネズミが掛かっていた。目的のヒヨドリはなかなか思惑通りに掛かってくれなくて、山の神様の気まぐれなご褒美を待つようなものだったが、何かを期待しながら過ごす日々は悪くはなかった。
ヒヨドリを捕るのは食べるためだったが、メジロは飼うために捕った。僕は自分では出来なかったので兄のやり方を見ていただけだった。まず鳥もちを作る事から始めた。秘密の木を兄は知っていて山の何処かからモチノキの樹皮をナイフで剥いできた。川の石の上で兄はその木の皮を叩いて潰した。最初は大まかにやがて丁寧に。潰しきれない不純物を水で洗い流し、そしてまたこつこつと叩き続けると粘り気が強くなってくる。仕上げに兄は口に入れてガムを噛むように何回も咀嚼し、何回も薄茶色の唾を吐いた。口から取り出す頃には滑らかな純度の高い鳥もちの出来上がりだ。僕も噛んだ事があるが大層苦いものだった。
兄は適当な木の枝を折って鳥もちを塗った。自然の枝に見えるように気を使う。その枝を竹竿の先に結びつけてメジロの来そうな椿の木の枝の横に立てかけておく。こうして捕ったメジロを兄は四角い竹籠に入れて大事に飼っていた。学校に行く前に蒸かしたサツマイモを餌として与えるのが日課だった。兄は竹籠も自分で作った。竹の筒を縦に細かく裂いて竹ヒゴを作りナイフでささくれを削り、別の竹の棒にキリで穴を空け竹ヒゴを差し込んでいく。それらの作業を幼い僕は尊敬の面持ちで眺めていた。うちは三毛猫を飼っていた。なぜか母は白と黒と褐色の三毛猫にこだわっていて、それ以外は飼おうとしなかった。だからうちの猫は代々「三毛」という名前しかない。この三毛がいるために鳥籠は安全な軒下の高い所に吊るされていた。ある時、メジロを狙った三毛が柱によじ登り鳥籠に向ってジャンプした。鳥籠に届きはしなかったものの兄は怒って三毛を捕まえた。嫌がる三毛の鼻先を鳥籠に何度も何度も擦り付けて、やってはいけない事を教え込んだ。兄のメジロより三毛の方がかわいいと思っていた僕は、鼻が擦り切れるんじゃないかと心配で泣きだしそうになった。実際、この頃の僕は何かにつけてよく泣いていた。
旅芸人の一座が来る事もあった。五六人の家族で構成された一座だった。集落の中心にある公民館が急ごしらえの劇場に変わるのだ。夕方の公演を知らせるために一座の数人が旗を立てて、太鼓を叩きながら昼過ぎの集落を回った。派手な衣装に白塗りの顔で頭にはちょんまげのカツラが乗っていた。チンドン屋を思い出してもらえばいい。一座には子供達もいて、狸のぬいぐるみを着て大人達の後を歩いた。こんな珍客に興味津々な僕たちは、少し距離を置きながらぞろぞろ付いて歩いた。公演は娯楽の無い大人達にとっても楽しみだったに違いない。出し物は股旅ものの芝居や歌謡曲に合わせて踊るものなどだった。いつもは殺風景な公民館がこの日は晴れがましく賑わった。一座は公民館に二三日泊まり込んだ。その短い間に一座の子供達と仲良くなり、相撲をとったりトンボを追いかけたりする子もいたが、なかなか打ち解けられない僕は遠くから眺めているだけだった。
公民館はほんの一時ではあるが託児所になったこともあった。毎朝隣の子が僕を誘いに来た。母に弁当を持たされた僕はその子と狭い草道を公民館に向った。僕たちの先生役は土地の人ではなく他所から引っ越して来たおばさんで、僕たちの言葉と違うイントネーションで話した。彼女には僕と同い年のほっそり背の高い男の子がいて、小さな小屋みたいな家に住んでいた。二人きりで住んでいるその家に僕はよく遊びに行った。家の前は小さな畑になっていて、その畑の前は谷になって川が流れていた。庭にはサクランボの木があり煌めくような実をいっぱい付けた。垣根には珍しい時計草がいっぱい絡まって濃い緑の壁のようだった。夏にはエキゾチックな白い花を咲かせ、やがて卵形の実を付けた。実を割って口にしたが酸っぱかったという記憶しかない。ここには僕のうちには無いものが沢山あった。教育熱心だったおばさんは子供に本を買ってやった。学習雑誌みたいなものや童話も僕には珍しかったし、蓄音機があるのはうらやましい限りだった。おばさんはうちの父や母みたいに一日中農作業をすることもなかった。何で生計をたてていたのか、集落の中では何だか特別な存在だった。
二人がいつの頃から僕らの集落に住むようになったのか解らないが、出て行く時は覚えている。確か小学四五年生の頃だった。男の子とは同じクラスではなかったが、学校の廊下で先生が元気でねと声を掛けていたのを憶えている。彼は成績も良く真面目だったし穏やかな性格だった。僕らは学校から一緒に帰る事が多かった。まっすぐ帰らずに山の方の道を遠回りして帰ることもあった。季節によって、山ではグミやアケビや山桃や野いちごや栗などのおやつが待っていたからだ。桑の実も好きだった。よく熟れた濃い紫色の実を摘んでポケットに入れたまま遊びに夢中になっていると、ポケットが潰れた桑の実のジュースで黒くなった。勿論食べた後は口の中も黒っぽい紫色に染まった。僕らは仲が良かったので喧嘩をしたことはなかったが、たまに僕がからかうこともあった。例えば彼の名前を反対から逆さに呼ぶとか他愛無ないものだったが、彼は怒らずに困ったような悲しそうな顔をしたので、僕は意地悪な自分が恥ずかしくなったものだ。
引っ越して行く前の日、彼はサクランボの木を一株持ってきてくれた。うちの庭にちゃんと根付くように木には根をいっぱい付けてくれていた。堅い庭の土を深く掘リ起こすのは大変だっただろう。最後に彼と何を話したのかは全く憶えていない。友達が他所に行ってしまうのは取り残されたようでちょっと惨めな気分だった。幼い頃出会っては別れ、そしてまた大人になっても出会って別れた沢山の人達。次々と顔が浮かんでくる。意地悪だったいじめっ子も迷信深かった婆さんも勧進どんも、多分、今まで会った人達は皆、僕の一部なんだ。
きょうは朝から風が強くて、街路樹や電線がびゅうびゅう唸っていました。商店街を歩く時は、古い店の看板が吹き飛ばされてくるんじゃないかと心配しながら歩きました。嵐のような強風のせいで駅まで歩くのにいつもより時間がかかり、電車にぎりぎりで間に合いましたよ。
きょうも荒川での写真です。古い杭と新しい杭のある風景。新しいうちはどれも同じに見えるのに、時間を経て行く段階で朽ち方にこんなに差が出てくるんですね。朽ちた杭の先端に雑草が根を張っているのを見ると、たくましいなと思いながらも、なんでそこやねん、とツッコミ入れたくなります。
あ、ツッコミついでに、傲慢な都知事にタカ&トシ風にツッコミ入れると、こうかな......... 横柄か!!
さて、アホな事言っとる場合ではないな。暑くなる前に作品を作らなきゃ........悔いが残る。


友達に貰った本があります。「これならわかるアートの歴史」ってタイトルで、ジョン・ファーマンというイギリス人の書いた10年前の本です。はじめのとこだけ紹介ね。
つい最近、アメリカの偉大な漫画家でフリッツ・ザ・キャットの生みの親であるロバート・クラムの言葉を目にしたが、その内容があまりにも辛辣なので思わず笑ってしまった。と同時に、彼の言ってることが正しいのかどうか、あれこれと考え込んでしまった。クラムいわく、「芸術なんてただのバカ騒ぎさ! 芸術家と呼ばれるやつらが大衆をコケにしているのさ。やつらは自分達を祭り上げ、象牙の塔にこもった軟弱な学者や、「芸術家がいるからこそ、この世界があるのだ」と考えている甘ったるい批評家たちにおだてられているだけさ。
こんな書き出しではじまるんだけど、あなたは笑うかな、怒るかな......
ラスコーの洞窟の絵に関しては次のような調子。
専門家によれば、これはワラ人形に釘を刺すのと同じく、獲物をしとめるための呪術のようなもので、絵が描かれている洞窟は、神殿や寺院であったらしい。私自身は、これは女房子供に自分の頭の良さと勇敢さを見せびらかそうとする男の見栄ではないかと思う。オジさんが、釣り上げた魚を抱いている写真を額に入れて、暖炉の上に飾っているようなものである。
なんて調子なんだけど.....ね。
自分の作品展に関してのコメントで「私の精神世界を感じて欲しい」と書いていた人がいたけど、そんな事、作者が要求するもんかな? アンタの精神だの世界だの知るかい! 作品次第だよ、って僕は独り言を言ったんだけど、そんな皮肉屋の僕にはオモシロい本でした.....とさ。
きょうも荒川の写真です。


友人や知人の個展を観に四軒のギャラリーに行きました。ひさしぶりに観た知人の作品が、今までと相変わらずの部分を残しつつも大いに変わっていたので新鮮でした。これで良いのか変わる前が良かったのか、まだ僕のなかでは保留。でも新鮮な驚きだったのは事実だから、多分これでいいのだ....。
判断を保留するなんてあまり無い経験です。とまどいつつも、オモシロいなと思っているのは良しということであるか...。彼女の作品はね、美術なんて「高尚な趣味」のない人には「うちの幼稚園の子供でもこんなの描くよ」って言われそうな作品ではあります。他人事じゃないけどね.......。
きょうも荒川の写真です。


きょうも荒川での写真です。
こんな水際を歩きたがる人がいるんだな。他人の事は言えんけどね。それにしても靴の位置が妙だ。歩き方が変じゃない?
濡れた砂踏みしだかれて色あたらしこの水際を行きし人あり、なんてね。釈超空のパロディです。誰ですか? 釈超空って釈由美子のおじいちゃんですか、なんて言う人。
話は飛びますけど、先の都知事選の頃、僕の周りでは石原批判がほとんどだったんだけど、結果は圧倒的な勝利でしたね。今思うと、あの頃僕が話した人達は都民ではなかったんだな......Oさんは埼玉だしHさんは神奈川だしなあ。宮崎県知事の言う「東京の傲慢は復活した」発言はまさに「そのまんま」だよね。言い直す必要ないと思うけど。地方の知事を田舎モンだの、宮沢元首相は野垂れ死にだの恥ずかしげもなくよく言えるもんだ。普通の神経だったら、こんな事言った途端に後悔して赤面ものだけどね。
ついでだけど、細木数子センセーも赤面しない人だろうな。なんで多くの人があんなエラソーな態度の二人を支持するんだろ、理解に苦しむよ。オコリンボーでイバリンボーで鼻持ちならないと思うんだけどなあ。以前、みのもんたのエラソーな態度が嫌いだと書いた事があったけど、この二人に比べたらカワイイもんた.......じゃなくてカワイイもんだ。


きょうも水辺の写真です。河川敷の濡れた砂の上を歩く時は、汚れても良いように古い靴を履いて出かけます。だから靴底がかなりすり減っていても、雨の日に少し水が染込むようになった靴でもすぐには捨てないんです。この写真を撮った日も古いブーツを引っ張り出しました。夏場だったら、裸足になってジーンズの裾をまくって水の中に入って撮る事もあります。でも裸足だとちょっと危険ですね。ガラスの破片でもあったら怖いし、プラスチックのエッジでも僕のヤワな皮膚くらい切れそうだし。子供の頃はよく裸足で遊んだものです。あの頃は足の裏が厚かったな。田舎の道には危険なモノは落ちてなかったし、まあ、危ないのは野バラの棘くらいという平和さでした。
それにしても、川にはいろいろな物が落ちてると言うか、捨ててあると言うか。自転車、バイク布団、冷蔵庫、果ては犬の死骸まであります。僕はゴミを好んで撮るような「悪趣味」なので、犬の死骸とか骨だらけになった鯉なども一応撮ります。でも、そんな物を皆さんに見せる程「悪趣味」ではないので安心してね。
こんなに穏やかな風景に見えて、実は水や砂の下には何か良からぬ物達が隠されているのかも......なんて良くない想像をしていたら気が重くなったので、上流からどんぶらこと桃が流れてくる呑気な絵でも想像しようかな。でも............桃にはすでにヒビが入っていて、そこから浸水し始めてる....中の赤ん坊が危ない! って........あらら、また良くない想像。やっぱりダメじゃん!


きょうは雨なので写真の整理。いつもそうだけどこの時期、ゴールデンウィークとは無縁な普通の休み。
きのうも普通に荒川の河川敷を散歩。こちらに越して来てからもう約20年過ぎました。引っ越して来た当時まだ小さかった水辺の木が、見上げるような大きさに育っているのを見ると改めて、20年か.....と溜め息。水辺の木は根元を水で洗われて、根というより下に伸びたたくましい枝ですね。地上に伸びるよりまず下を安定させようと頑張ってる。いや、別にね、木を擬人化して教訓を垂れようとか思ってないですから.....そんな気恥ずかしい趣味はありません。だたひたすらこの姿に感心しきりのワタシです。
ところで、うちの蛸足配線だけど......大丈夫か?


28日土曜日、久しぶりに舞踏を観ました。阿佐ヶ谷での上杉貢代さんの公演。若い二人を従えての舞踏だけど、やはり彼女はソロがすばらしいな。以前から、舞台にすっと独り立っているだけで絵になる人だと感じていましたが、今回は鍛えられた身体、筋肉のひとつひとつの動きにさらに凄みというか「説得力」が加わったような気がしました。これは年齢を重ねたからこそ得られるものかもしれないな。うーん、いろいろ事情があるのだろうけど、ソロだけ観たいというのが正直な感想。それも、もっと広い舞台でね。彼女には「花」があるからそれをもっと生かせる所でやって欲しいな。
公演の後、十数人で飲み屋に移動。僕は最近滅多にこういう付き合いはしないのですが、友人も一緒だし友人に舞踏の人二人を紹介してもらったし、あしたは日曜日だし、って事で焼酎を随分飲みました。上杉さんも顔を出して5年ぶりだねって挨拶。友人が彼女のプロデュースをやっていた頃はよく観ていたのですが、随分ご無沙汰だな。まあ、舞踏の様式化された動きとかに飽き飽きしてた事もあって、昔の「熱狂」が醒めた部分がありましたしね.......。でもね、いいものは、いいんですよね。舞踏でも美術でも、どんなジャンルでもひとくくりには語れない「個人」がいるんだ.....。
舞踏は、人の身体を凝視させる表現だと僕は思っています。以前からトルソとか「ひとがた」に興味があって、今回の公演を観てさらにヒントをもらいました。何を観ても聞いても結局自分の作品に結びつけちゃうのね。浅ましいというか、熱心と言うか......。
三人展が終わって、きょうはのんびりしています。会場に夜7時まで一週間居たので、帰って風呂に入って飯食って寝るだけの毎日でしたから、楽しいけど疲れました。今回は趣向を変えてインクを使ったのですが、インクで描いたと言うと驚いた人がいました。カラーインクの存在を知らない人が意外に多いのには、こっちが驚きますよ。それもね、絵を描いてる人が知らないなんて。画材屋さんには行くのでしょうが、油絵の具とキャンバスにこだわる人は.....そんなものかな。
「僕の技法」? について「企業秘密でしょうね」と言う人もいたらしい。そんなもんありますかいな。インクを吸収しにくい光沢紙を使うと、インクが乾く間に釘や割り箸やらで引っ掻いたり、指や布で擦ったり作業出来ます。水彩紙でも、あらかじめ紙を湿らせておけば乾きを遅くできます。でもケント紙とかすべすべした光沢紙の方が線のスピード感がでますね。今回はそうして作ったドローイングの上から樹脂でコーティングしました。インクの定着が良くない光沢紙を使ったので保護するためと、透明感が欲しかったからという理由です。アクリル絵具の「軽い」光沢が好きではなくて、ずっと光沢を抑えた作品ばかり作ってきたので、それへの反動もあるかな。
さて、今年は夏のグループ展に誘われているくらいで他の予定は今のところありません。来年は一月の個展が決まっています。ずっと先の話だからって、サボらないようにしないとね。


さっき三人展の搬入を終えました。あしたから始まるのですが、実は案内状が足りなくなってしまいました。この日記を読んでもらってる人には「ここ」でお知らせした、という事で出しませんでした。ごめんなさい。
今回はインクを使ってのドローイングにしました。初めは立体のためのドローイングのつもりだったのですが、これはこれで結構おもしろいですよ。インクを使ったドローイングなので、題して、ドロー「インク」ってのはどうだろ.......


個展の会場に居るといろんな人が来てくれます。ただギャラリーをぐるっと一瞥して帰るだけの人もいれば、作品の台の下までしげしげと眺める人もいるし、あきらかにオープニングパーティの酒が目的の、正体不明の人まで様々。「評論家」という正体不明の人もね........
気になるのはやはり作品をろくに見もしないで出て行く人。僕なんかあまり興味のない作品でも、一応は注意深く見るけどね。あまり好きではない作品でも、オレはなぜこんなモノを作らないのか、なぜ気に入らないのか改めて確認できるからね。作品自体に限らず、展示の方法とか何かしら学ぶ事はあるよね。あ、学ぶって言うよりヒントになる。実に些細な事だけど、学ぶというのはどうもニュアンスが違う気がする。僕はあまり学んでこなかったけど、いろんな作品からいっぱいヒントを貰ってきたんだ。それを学ぶっていうんだって......? そうかな.....。
花見で浮かれる事もなくなって久しいな。作品を作る方が楽しいと言えるのは良い傾向。近くの公園の、散り始めた桜の木の下で花見をしている人達を横目に見ながらさっさと帰ります。まだ三人展の案内状も出してないな。個展と違って、ちょっと気楽に呑気に考えちゃってます。でも手抜きの作品は出せません。これでも、僕は負けず嫌いで? 他の二人に見劣りするようなモノなんて絶対出せないもんね。
きょうも個展の時の写真をUP.


きょうもインクでドローイング。あら、これは作品としてなんとかなりそうな感じだ。それよりなにより愉しいのがいいな。意図しないインクの滲みとか混ざり合う色がきれいです。こんなふうに偶然を利用しながら作るのは久しぶりなので新鮮なんです。単なる偶然だけの作品にはあまり興味ないから、この偶然をいかに自分のイメージに引っ張り込むかが肝心でオモシロいところです。
きょうも個展の時の写真をUP。


もう四月か。来週は三人展がはじまります。今回の個展は立体だけの展示で「苦手」の平面は二点
だけにしました。だから? 楽しかったな.......。平面の作品は余程新しい事を始めないと、マンネリからの脱出は難しいな。少し距離をおいたら何かしら新しい事ができるかもしれない。あるいは新しい「気持」で始める事ができるかもしれない......解らないけどね。このところ三日間試しにイン
クでドローイングをやっています。指や割り箸でインクや紙を擦ったり引っ掻いたり、オモシロいけど作品にまで出来るかどうか?
さて、個展の作品を少し紹介しておきますね。


個展まであと2週間しかないのに、ちょっと作品が停滞気味です。納得のいかない作品を出すわけにいかないのでもうひと頑張り。もう十年以上前になるけど、気に入らない作品での個展が苦痛だったのを思い出しました。普通ならたくさんの人が見てくれるのは嬉しい筈なのに、その時は会場に居るのが嫌で、悔しくてね。そんな時は、たとえ気に入ってくれた人がいたとしても、気恥ずかしいだけで素直に喜べないものです。
自分にとって、生きる事は学ぶ事だと言える人が羨ましい。そうなのかもね。僕は怠惰な人間なのか傲慢なのか、そんな事照れくさくて言えないな。僕にとって、生きる事は作品を作る事だってマジで言ってみたいもんだ。ひねくれ者のもう一人の自分が、いつの頃からか僕の内には住み着いているので、そんな自分をせせら笑うんですよ。困ったものだ。愚直なまでに一途な人に憧れたりするけど、そんなの無い物ねだりだって........。
 |
平原辰夫展2007.3.19(月)-24(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 金曜日は20:00まで開廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座6-10-10第二蒲田ビルb1f tel 03-5537-6988 ●地下鉄銀座駅下車(A3)出口  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |
立体の作品を集中して作っていると、平面の作品への興味が薄くなります。今回は立体だけの個展にしようかと思ったりしています。でも画廊の方へはプランとして、立体と平面の両方として提出済みだしなあ。ヘンテコな立体達を並べて見ていると、何処からこんな発想が出て来るんだか、我ながら
妙な気分になったりします。「オレが作ってるんだ」というより、何かの媒体になってるような、そんな気分。いつの間にか自然と出来ちゃうんだ。勿論、あれこれ考えるのも作るのも自分なんだけどね。まあ、個性という言葉を使えば、個性なんて出すもんじゃなくて出ちゃうもんなんでしょうね。
自分に備わっているモノだけが個性じゃなくて、欠けているモノも合わせて個性って事なんだな....。
ラジオを付けっぱなしで作業中、急に子供の頃の事を思い出しました。子供の頃は、山や川や田畑や道端など何処でも遊び場でした。ちょっと高い場所から、例えば岩や樹の上から跳び降りる時によくこんな事を言ったものです。歌うように節をつけて言いました。
「跳ぼかい、泣こかい、泣っよかひっ跳べ!」
跳ぼうかそれとも泣こうか、えーい、泣くより跳んじゃえ! という意味です。あまり高くない所から跳び降りる時はわざわざ言いません。ちょっと危険を感じるし怖いけど、でも勇気を出せばなんとか跳べそうだなというくらいの高さの時です。何十年ぶりかで思い出したこんな言葉で、当時の映像が走馬灯のように、って....おお.....なんと陳腐な表現なんだい?
そういえば、大江健三郎は「見る前に跳べ」って書いてたっけ。見てしまったら怖くて跳べなくなるか、それとも見てしまったのだから跳ぶ必要性を感じなくなるか。まあ、いずれにせよ僕の場合は、理屈を言う前に作れ、ってとこです。
ひさしぶりに写真をupしようかな。カメラに触る余裕がしばらくは無いなあ。

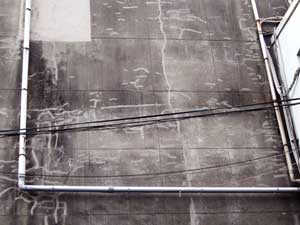
きょうも紙をちぎったり貼ったり木を削ったり。これって確かに、いわゆる「絵描き」のすることではないな。僕は絵描きではないか。まあ、肩書きなどドーでもいいんだけど、真面目に訊かれたら困りますね。立体でも平面でも、現実にある物をもとにして作っているのではないので、まともに答えるのが難しいです。抽象ですか? と訊かれたら、そうですって答えてますが..........。でも、実感としては抽象ではなく、非常に具体的なモノを作っているつもりです。日常には無いけど、ほら、ここには実際にあるでしょ? 現実に目の前にありますよね。抽象って観念的すぎるんだよね。モノの本質をとらえるみたいな......僕には本質なんて解らないよ。絵の本質も音楽の本質も自然の本質も人の本質も解らない。むしろ、表層がオモシロい。この際だから言っちゃうけど、人だって物だって、本質なんて言ったって表層に出るもんさ。出なきゃ誰が何を手がかりに本質にせまれるんだよ、と言いたい。隠れっぱなしの本質なんて、押し入れに永遠に仕舞ったままの、誰の眼にも触れる事の無い僕の「大傑作の作品」と同じじゃ! 意味ないじゃん。じゃんじゃん、とオチの音楽が鳴る.....。
政治家の本質とやらも、行動や失言というかたちで表層に出るでしょ。アンタ等国民はな、親類縁者を除けば、アタシ等が思いのままに操る将棋のコマのひとつにもならんくらいの、まあその程度のモンよ。
はあー 酔ってます。個展の差し入れにお酒を沢山いただきました。ワインが多かったな。最後のチリの赤ワインが美味しくてつい一本空けました。まだ日本酒が一本とブランデー二本残っています。個展の後はいつもですが、しばらく酒屋と付き合わずにすみます。えーっとですね、僕の本質は飲ん兵衛ではありません。でも本音は日本酒よりワインの差し入れを下さい、です。ほらね、ちゃんと表層に出るもんでしょ? うは........強引なオチや、というか、ただの「おねだり」じゃん。
他の人の作品に共感出来るのは嬉しいものです。でもあまり自分に近い感覚の作品はオモシロくないな。たまにそんな事があります。自分の感覚に近いと感じるのに、随分異なる表現をしているなと思うくらいの方が興味深いです。例えは相応しくないかもしれませんが、僕が自分の故郷の風景をきれいだと見直したのは、故郷を離れてからでした。毎日眼にしている山や海は美しい景色ではなく、当然ある景色でしかありませんでした。まあこんな具合で、あまりに身近過ぎると興味を惹く対象にはなりにくいです。
その身近な対象の最たる物が「自分の作品」ですね。今回の個展は初めてのギャラリーだったので、見てくれる人も初めての人が多くて、結構熱心に見てもらえて嬉しかったのですが、正直なところ僕にとっては「退屈な風景」ってところ。言い過ぎか? 良い作品だと2回も足を運んでくれた人がこの文章をを読んでなきゃいいな.......って、じゃあ書くなよ、と言いながらカットしないもんね。
今は立体の作品を作るのが楽しい。まだ「退屈な風景」にはなりそうにないけど、いずれはそんな日がやってくるんだろうか? それはそれで良し。何か新しいものに出会えば、僕も作品も当然変わります。
僕には他人を啓蒙するような立派な思想や哲学なんぞないので、ねえねえ、こんなの出来ちゃったんだけど見てちょうだい......と、こんな調子でひたすら作り続けるのがお似合いです。
さて、気分を新たに3月の個展に向けて作品を作らなきゃ、時間がない。
「子供を産む機械」にはなれないから、「作品を生む機械」にでもなりますかね。でも、やはり機械はまずいな。感情を排したクールな作品に惹かれた時期もあったけど、今はある種の感情が感じられる作品がいいな。感情を否定する事は人間性の否定につながるんじゃないかな? まあね、短絡的に語るのは危険だけどさ。たとえ機械を使って作品を作っても作るのは人間で、見るのも人間だったら、そこには当然「感情」というものが介在してくるんだ。人が人であるかぎり「感情」からは逃れられないんだと思うよ。でもはっきり言って、あまりに「感情的」な作品とも人とも僕は付き合いたくはないぜ! そんな付き合いより、人の事になど全く無頓着な星空でも見ている方がよっぽど和む。ふむ........僕は人間が好きかと訊かれたら、「好きです」と普通に答えるだろうけど、「ホントに?」と訊き返されたら「あまり好きじゃない」って言うかも.........おお....でもね、機械にはなりたくないですわ.......。
個展の時の立体の作品を紹介しておこうかな。


先週個展が終わったばかりなのに、ずっと昔の事だったような気がする。時間の感覚が麻痺してしまっている。
5日月曜日の夕方に、奥さんからの電話で友人の死を知らされた。友人というか、僕の兄貴のような存在だったな。二十歳の頃からの付き合いだから35年の付き合いになる。当時は歩いて行ける程の近くに住んでいたのでよく行き来していた。新宿のゴールデン街は彼の庭みたいなものだったので連れて行ってもらったし、美術館や能楽堂にも一緒に行ったものだった。僕よりちょっと上の世代、団塊の世代の彼は何事にも過激だったな。例えば、お酒だったらアル中になるまで飲むし、政治的な話など喧嘩になるから、僕は恐くて話さないと決めていた。家を建てる時は一流の建築家と対等に話せるくらい勉強していたし、子供のための絵本でも掃除機を買う時でも、もの凄い資料や本をいつもカバンにずっしりと入れていた。僕と全く反対の性格だったけど、だから付き合えたのかもしれないな......。
去年の暮れにお酒を持って僕の所へ来て、近いうちに二人展をやりましょうと話したばかりだった。
奥さんの話だと、ちょうどその後に具合が悪くなって入院したらしい。いつも個展に来てくれるのに来ないから心配はしていたが、まさかこんな事になるとは思っていなかった。
身内だけで静かな葬儀をやりたいという奥さんの希望だったから、一人の親しい友人に知らせただけで他には連絡しなかった。きのうの葬儀は本当の身内だけの葬儀で静かだった。しゃらくさい事の嫌いな彼らしいや。痩せて老人のようになった顔を見ていたら泣けてしかたなかった。
生あるものが死ぬのは必然だが、それでも、いつでも死は不思議だ。
生きている事もまた.........不思議だ。
 |
平原辰夫展2007.1.29(月)-2.3(土)11:00AM〜7:00PM (日曜休廊/最終日4:00PMまで) 中和ギャラリー 〒104-0061 中央区銀座6-4-8 曽根ビル3F TEL 03-3575-7620 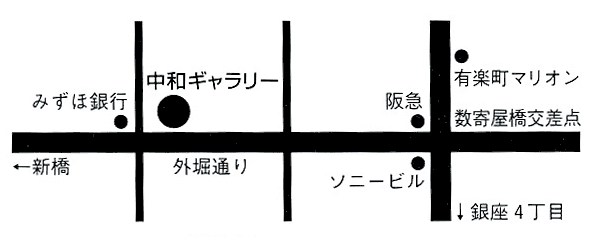 地図をクリックすると拡大できます |
あけましておめでとうございMすう.....

おっと、指がどうも不自由でうまくキーボードが押せません。暮れの忙しい時に左手の人差し指を包丁で、爪の上から切ってしまいましてね。布巾を裂いて包帯代わりにきつく巻いて仕事しました。指を動かさないわけにいきませんから治るのが遅いです。妙な切り方をしたので、爪が伸びるまでしばらくはバンドエイドで留めておくしかないな。
正月もお酒をひかえ早寝早起きで作品作りです。今月末の個展と三月の個展、四月の三人展と続きますから忙しいです。だらだらするよりは忙しいくらいの方がいいけど、それにしてもちょっときついです。
さて、きょうもそろそろ寝て早起きしなきゃ。
年賀状を出していませんが、今年もよろしくお願い致しMすう.......。