
三 人 展
平原辰夫・橋本憲治・岡村光哲2014.4.1(火)-4.6(日)
12:00〜19:00まで
(但し最終日は17:00まで)
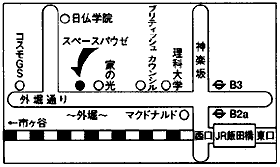 gallery space pause
gallery space pauseギャラリー スペース パウゼ
〒162-0826 新宿区市谷船河原町9
会場 tel 03-3269-5007
事務所 TEL/FAX 03-3269-7008
●JR飯田橋(西口)、地下鉄有楽町線、南北線(B3,B2出口)より徒歩5分
信号一つ目手前
作品画像および地図をクリックすると拡大されます
「花火の日」
僕は小学生の頃までは章太やその兄弟とよく遊んでいた。家は近くはなかったが、僕が彼らの所まで「遠征」していたのだ。ランドセルを背負った僕らは、鉛筆を削るためのナイフを必ず筆箱に入れていた。しかし、鉛筆を削るより遊びのために使う方が多かったので、すぐに切れ味が落ちて、砥石を使うのも自然とおぼえた。山から竹を切り出して水鉄砲や竹とんぼを作ったし、忍者ごっこのための刀や弓も作った。章太は器用で僕のための刀も作ってくれた。竹を半分に割って、それを細く削って接着剤と紐で二枚張り合わせ、本物の刀に見えるように切っ先まで丁寧に作った。僕は「実戦」でそれを使うのが勿体なくて腰に差したまま、戦う時は自分で作った刀、つまりただの丸い竹の棒を使った。
四年生と五年生の時に同じクラスになった章太は、クラスのみんなの推薦でいつも学級委員に選ばれた。この頃ほんの短い時期だったが、父は豚を飼ったことがあって、僕も餌をやったり小屋の掃除を手伝っていた。ある日学校で誰からともなく臭いと言われるようになった。僕が給食の当番になった週などは、臭くて食えねえと言う奴までいた。僕は先生に言われたとおり石けんで手もちゃんと洗っているし、白衣と帽子とマスクも着けている。文句を言われる筋合いなどない。それに父にとって初めての養豚なので、神経質なほどきれい好きで豚を大事に育てていたし、僕が小屋の掃除をサボるとよく言われたものだ。「動物は本来みんなきれい好きなんだ。豚小屋が汚いというのは飼い主が悪い」
父の言う事は本当だと僕は知っている。僕の事を臭いとか言う奴は、何にも解ってない奴なんだ。まともに相手にする必要はない。でもそんな風に自分に言い聞かせても、悔しいのは悔しい。僕はケンカは嫌いだが、一度だけ我慢できなくて拳を握りしめたことがあった。章太はそんな僕の代わりにみんなの前で「本当に真ちゃんが臭いかどうか、嗅いでみろよ」といつになく声を荒げて凄んでみせた。今までそんな章太を見た事がなかった。僕はそんな風に言えない自分を恥ずかしく思ったし、「章ちゃん、ありがとう」とさえ言えなかったが、章太は何事もなかったように「帰ろう」と僕を誘って一緒に帰った。
中学生になると章太はタバコを吸い始め、町をうろつき始め僕のよく知らない仲間と遊ぶようになり、クラスも違ったので顔を会わせても話をすることもなくなった。真面目で成績も優秀で僕らのリーダー的存在だった彼が、次第に荒っぽい態度を身につけるようになると近付き難かった。そんな彼もたまにすれ違う時、今の俺はもう昔の俺とは違うのだとでも言いたげな不敵な笑いを、あるいは少し照れたようにニヤッと笑顔を向けた。僕も同じように笑顔だけで挨拶した。今でこそ先生や生徒達に不良と見なされているが、数年前まで一番仲の良かった僕をどう思っていたのだろう。言葉のない奇妙な笑顔だけの挨拶だが、何となくお互いを了解していたような気がする。
「章ちゃんのお母さんが入院したそうよ」母は台所でそう言った。大分おかしくなってはいたらしいけど、もう手が付けられないそうだと言った。訳の解らないことを口走り暴れる事もあるのだと。僕はそこで初めて章太の家庭の深刻さを解った気がした。でも僕にできることなど何も思い浮かばない。何と声を掛けていいのか.....解らない。自分の母親がそんな状態になったとしたら、そう思っただけで胸が苦しくなる。坂の上のみかん畑から「これ食べなさい」と言ってみかんを投げてくれた、あの元気な頃のおばさんを思い出す。おばさんはいつも田畑で忙しそうに働いていて、章太とその兄弟も仲良く手伝っていた。そんな彼らを「偉いねえ」と母が褒めるたびに、あまり家の手伝いをしない僕はいつも肩身の狭い思いをしたものだ。
町の中央を横切る高州川は台風のたびに濁流が流れ、河川敷の草木を呑み込み土手の土を削り取った。町の中心に掛かる橋のたもとに飲み屋ができた。川に因んだのだろう「多加巣」という店だ。子供の僕らは飲み屋などに何の興味もなかったが、何となくいかがわしい場所だと思っていた。たまに見かける女の人は派手な化粧で喰わえタバコだったし、出入りする男達も知らない人達だった。章太はここで酒もタバコも覚えたという噂だったが、子供同士の噂なんて本当かどうか怪しいものだ。しかし、職員室や校長室に何回も呼ばれていたから、どこかで何らかの問題があったのだろう。
でも、問題って何だろう?大人だからという「単純」な理由で、先生達は普通にタバコも吸うし、おそらく「多加巣」で酒も飲むのだろうし、喰わえタバコの女の人とふざけた話もするのだろう。同じような事をしている人間が、章太を頭ごなしに責めるのはどう考えてもおかしな事だ。せめて、お前の気持ちは解るけどなと、ほんの少し理解の気配ぐらい示してもバチは当たらないだろう。先生でも同級生でも誰でも、僕は偉そうな奴は嫌いだ。僕は職員室に呼ばれた事はないけど、先生達だって人間だ。生徒達の間に「幼い」確執があるように職員室にも「大人」の不和がある筈さ。そんな事を想像している僕は勉強に身が入らなくて、この頃は図書館で本ばかり読んでいた。章太とは全く違う方向だが、僕も「もっともらしい場所」から少しずつずれて行きそうだった。僕はおとなしくて、章太のような行動する不良ではなかったが、堅苦しく真面目くさったものをあざ笑うような気分が、僕の中にも生まれ始めていた。
高州川の花火大会は、子供達ばかりではなく大人達にも楽しみなものだった。小学生の頃は父や母と出かけたが、中学生になるといつも近所の友達三人と一緒だった。花火自体も楽しみだったが、提灯を下げたいろいろな屋台を覗くのもまた楽しかった。かき氷りんご飴綿菓子など、それにいい匂いで食欲をそそる焼きそばやイカ焼きなど。様々な誘惑に迷わされ、少しばかりの貴重なお小遣いを何に使うか決めかねる事が多かった。母は僕を子供扱いして「冷たいものばかり食べてお腹こわすんじゃないよ」と言って小遣いをくれた。「ハイハーイ、解ってるよ」と僕が面倒くさそうに言うと「ハイは一回でいいの!」と母が言うのだ。
花火大会が始まるまで、いつになく華やぐ町をぶらついた。同じクラスの女子数人が浴衣を着ているのに出会ったが、着慣れないせいで歩き方がぎこちなく見えた。でも教室にいる時よりも大人っぽいので、僕らは思わず振り返ったりした。そろそろ時間だから河川敷に移動しようと友達が言うので、川への薄暗い草の道を降りて行った。鈍く銀色に光る高州川はゆったり横たわり、町や両岸の人々のざわめきをよそにひたすら静かに海へ向っている。たまに水面に飛び上がる魚の音がすると、川が様々な生き物達の住処であることを今さらのように思い出す。
僕らは、打ち上げ場所にできるだけ近い所に座ろうと思った。砂と石ころと草を踏み、生暖かい風に吹かれて歩いていると、反対から歩いてきた人に危うくぶつかりそうになった。避けた一瞬、章太だと解った。しかし、章太は連れの女の人と話をしていたので僕に気付かなかった。暗がりで良かった。何を話したらいいか、どう対応したらいいのか、僕は戸惑うばかりだからほっとしていた。「今の章太だっただろ、飲み屋の女と一緒か?」と軽蔑したように友達は言った。その口ぶりに僕は少しむっとした。章太の母親の事を思うと、僕は非難めいた事を何も言えなくなるんだ。友達が章太の事を、さも解ったふうに言うのも聞きたくはなかった。もっとも、僕に章太の何が解っているのかと問われても答えられない。しかし、僕はいつも思っていた。「章ちゃんは確かに変わったけど、別な人になった訳じゃないんだ」
上流で何やら人々のざわめきが聞こえてきた。どうやら人が川に落ちたらしい。去年も酔ったおじさんが落ちたが、幸い浅瀬で事なきを得た。しかし、ざわめきは大きくなるばかりで、向こう岸のゆるくカーブした深い所を流されているらしい。騒ぎを聞きつけたらしく「多加巣」の方から数人飛び出してきた。その中の一人が服を脱ぎ始めた。手にはロープの付いた浮き袋を持っている。川面にしばらく目を凝らしているようだったが、確信した様子で飛び込んだ。遠くからでよく見えなかったが、やがて黒い影がふたつ岸に引き上げられた。みんなの安堵の溜め息が笑い声に変わり、花火の始まりの音が鼓膜を震わせ、火薬の匂いがつーんと鼻の奥を刺激した。もう誰もが花火に見とれて、川での出来事などすっかり忘れてしまった。
花火大会は仕掛け花火のナイアガラで今年も終わった。帰りは大勢の人波に流されながら橋を渡った。「おい、あそこでケンカしてるよ」友達が橋の下を覗き込んで言った。河川敷の砂場で六七人入り乱れている。「隣町の中学校のやつらとうちの学校の生徒だ」そう言って、友達は高みの見物とばかりにずっと眺めていた。僕は興味が無いのでひとりで帰ったが、ケンカしている連中のなかに、章太がいなければいいなと思っていた。
帰りは町外れのガソリンスタンドの横の細い道に入った。近道なのだ。ここまで来ると花火からの帰りの人もまばらで、急に寂しくなる。いつの間にか犬が僕の後を歩いて来る。野良犬だろうか、時々振り向くと人なつっこい目で僕を見上げる。みすぼらしい姿だが以前は人に飼われていたのだろう、そんな目をしている。小学生の頃、章太の家で飼っていた犬に目と鼻が似ていると思った。走るのが好きでよく並んで駆けっこをした。若葉の山道やぬかるんだ田んぼのあぜ道も、特に柔らかなれんげの畑の中など走るのは最高だった。車に轢かれてあの犬が死んでしまった時、みかん畑の隅に僕も一緒に穴を掘り埋めてやった。みんなでかわいがっていたので、あの時が死というものを切実に感じた初めての体験だった。
僕はしばらく立ち止まって犬を見ていたが、「おいで」と呼ぶと近づいてきた。頭を撫でていると、章太と不良グループ三人がいつの間にか側に居るのに気が付いた。なんだか居心地が悪いので、章太に目だけで挨拶して帰るつもりだった。「汚い犬だなあ。どこのゴミ箱から出てきたんだ」ポケットに手を突っ込んだ一人が言った。もう一人がにやにやしながら花火を持っているのが見えた。僕はそいつのやりそうな事を考えて不安になった。火をつけた花火を犬に向けるつもりなのだと思った。そいつは花火を両手でもてあそびながら、なれなれしく犬と僕の横にしゃがみ込んだ。ポケットからライターを取り出すと、「汚い犬だな。熱消毒してやろうか」と言った。
それまでじっと見ていた章太が「やめろよ」と言って、僕がやりたくてもやれなかった事をやった。花火をいきなりを取り上げたのだ。紙製の筒から火花が噴水のように吹き出すと、章太は大笑いしながら他の三人に向けた。手で顔をかばいながら慌てて後ずさりする三人に、追い打ちをかけるようにロケット花火を次々発射した。
章太が先生や親達に不良と呼ばれても、僕にはそんなのどうでもいい。何と呼ばれようと「やっぱり、章ちゃんは章ちゃんだ!」僕はこの花火の日の章太を絶対忘れないだろう。
「やがて、星降る所に」
子供の頃私は墓地が恐かった。それは私だけじゃなく、たいていの子供達がそうだったのだろう。夕方遅くまで遊んで帰る時、薄暗い墓地のすぐ脇の道は走ったものだ。何人かで連れ立って帰る時はよかったが、ひとりの時は脇目も振らずに走った。墓地の近くを流れる小川のささやかな音さえも、竹やぶのざわめきも恐さを倍増させた。たまに頭上近くをかすめるコウモリの羽音などには思わず悲鳴をあげそうになった。墓石の陰からは、名も知らぬ死者達の視線や様々な思いがさまよい出てくるようだった。墓地にあるはずの数々の死は、自分には関わりのないおぼろげなものだが、目には見えない何か抗し難い圧力を持つもののようでもあった。
それでも、優しかった祖父が埋葬されてからはあまり墓を恐いと思わなくなった。祖母は私の産まれる前に亡くなっていて同じ墓地に眠っている。幼い頃私の田舎はまだ土葬が行われていた。大人も子供も色とりどりの旗の行列を作って祖父を墓まで送った。四角い木の棺桶は若者に木の棒で前後を担がれ、両側に田んぼを見ながらゆっくり坂道を下り、石橋を渡り小さな峠を越えて墓に着いた。それから深く掘られた墓穴にゆっくりと降ろされて、大量の土でこんもりと覆われた。母は埋められる祖父に向って「良い所に行きなさいよ」と涙声で叫ぶように言った。穴の縁まで近づいた母の足元からは、土塊が穴の底に向ってはらはら落ちた。父は無言でそんな母をじっと見つめていた。赤や黄色の旗が、竹に結ばれた十数本の旗が土の上に立てられた。それ以来、私はお墓を以前ほど恐い所じゃないと思うようになった。だって、あのおじいちゃんが居る所だもの。恐くなんかない。私は墓の近くを通る時、いつもおまじないのようにそう繰り返した。
祖父の葬儀が済んで数か月経った頃だ。私は小学生になったばかりで学校になじめなかった。先生や他の生徒達にどう接したらいいのか解らず、休み時間も所在なく落ち着かなかった。そんな頃、私の知らない街に住む父の弟である千次叔父さんが、ひと月ほど我が家で一緒に暮らしたことがあった。父と母は毎日田畑に出て働いたが、千次さんは手伝う事もなく、ふらっと何処かに出かけては夕方帰って来た。背は高いのに身体が細い。それに千次さんの手は白く細くて畑仕事などできるとは思えなかった。母はそんな居候の千次さんを不満に思っていたようだが、直接本人に言う程ではなかった。働き手としては劣った者と見なしながらも、どこか一目置いているような遠慮している様子だった。
私には妹がいた。妹は生まれつき脚が悪くうまく歩けなかった。右足が内側に曲がっていて、母は町の病院まで毎週一回妹を連れて出かけた。大人の脚で30分程だったが、妹の脚で田舎のでこぼこ道を歩くのは倍以上の時間がかかった。だが、妹は母と一緒に町に行くのが楽しみで、病院に行く準備をしながらはしゃいでいた。あまりに嬉しそうなので、私は自分の健康な脚をうらめしく思ったほどだ。山際の集落から賑やかな町に出る事は、もうそれ自体が特別な事だった。やがて私も小学生になり町の学校に通うようになると、羨ましいなどという気持ちはすぐに消えてしまったのだが。
私と妹は母の真似をして、千次叔父さんのことを千さんと呼ぶようになった。千さんは他の大人と違っていた。ノートに何やら書き込んでいたり、出かける時も本を持ち歩いていた。父や母も、それに周りの大人達にも本を読む習慣を持つ人などいなかったし、農家で本といえば「家の光」という農協を通じて配布される月刊誌くらいだった。千さんは驚いた事に貸本屋の漫画まで読むのだ。当時私の周りには漫画など読む大人などいなかったのだ。母は露骨に嫌な顔をしたが千さんは意に介さず、読み終えた漫画を後でこっそり私にも読ませてくれた。私は図書館の本も好きだったが、漫画の方がずっと面白いと思っていたから夢中で読んだ。千さんはこれなら文句無いでしょうとばかりに、母の機嫌をうかがうように、私には「世界の偉人達」という本を、妹には絵本を買ってくれた。本に関して母の基準は実に単純でこれは歓迎された。読んでためになる本とかならない本などの区別は私には何も無かったし、千さんも母の反応を少しの皮肉を込めて愉快そうに見ていた。
私達は学校に漫画を持ってきてはいけないと言われ、流行歌とか歌謡曲など歌ってはいけないと言われた。漫画は文学に対して、歌謡曲はクラシックに対して卑俗なものという扱いのようだったが、母はラジオから流れてくる歌謡曲が好きで台所でよく口ずさんでいた。私は楽しげなそんな母の顔が好きだった。そして私も妹もごく自然にたくさんの「いけない歌」を憶えた。ラジオからの歌って大人には良くて、子供のためにはならない歌だったのだろうか。私は歌詞の内容など考えた事もなかったし、言葉の意味もよくは解らなかった。初恋の花がどんな花か知らないし、哀愁列車がどんな列車か疑問にさえ感じていなかったが、歌をうたえば楽しい気分になる。それだけは知っていた。
千さんはノートに歌詞も書いていた。自分の作ったものかラジオからの聞き取りなのか、本からの写しなのか解らなかった。だいたい私には読めない漢字が多かったし、ちらっと見せてもらっただけで当時は興味もわかなかったのだ。罫線のないノートには文字も絵もあって、絵の方に私は惹かれた。私の知らない海辺や町のスケッチが、繊細な鉛筆の線で描かれていた。千さんは仕事も手伝わないで毎日ふらふらしていると母はこぼしていたが、実は期待もしていない口ぶりだった。自分達には無い千さんの才能を、あるいは人柄というものを認めていたのだと思う。ある雨の日、畑仕事を休みにして家で繕い物をしている母を、千さんはいつの間にか数枚スケッチしていた。母には何故か見せないでいたが私と妹に見せてくれた。それを見て、母さんってきれいなんだねと私は妹に言った。千さんは家を出て行く前日に、その中の一枚を母に渡したのだった。
ずっと後になって父に聞いた話だが、千さんが田舎に帰って来た目的のひとつは、ある人のお墓参りのためのようだった。ひと月も我が家にいたのは、隣町にあるその人のお墓に何度も行っていたからだ。私の田舎には略奪結婚の風習が残っていたらしい。略奪というのは文字通り盗むことで、ある若者が結婚したいと思う娘を、仲間達で示し合せて強引にさらってしまうのだ。たいていは形式的なもので、娘もあらかじめ知らされ両親も了解済みの事が多かったらしいが、たまにそうでもない場合があったらしい。千さんがまだ十八歳の頃で、お互いに好き同士の富佐子さんという同じ歳の娘さんがいたらしい。この話をする時「好き同士」という言い方を、父は悲しげな顔で口にした。富佐子さんは何の前ぶれもなく、いきなり隣町の自動車整備会社の息子と、数人の若者達に連れ去られ「傷物」にされたのだ。いまでこそ信じ難い犯罪だが、当時この地方では問題にされなかった。千さんはこんな田舎に失望し、二度と戻るまいと決めて憤懣やるかたなく家を飛び出したのだった。父は打ち明け話のように沈んだ口調でこの話をした。
富佐子さんは望まない結婚の後、五年後にこの地方の風土病で亡くなった。父も詳しくは解らないらしいが、昔からこの地域には独特の血液の病気があって、たぶん自分達にも同じような血が流れているのだろうと言った。千さんが田舎に帰って来て私達と一緒に過ごしたのは、富佐子さんの死から十年近く経ってからの事だ。二度と帰るまいと出て行った気持ちにどんな変化があって帰って来たのか、父にも解らなかった。「俺には......何も訊けなかったよ」と父は何か考え込み落ち着かない様子で言った。富佐子さんの略奪に、ひょっとしたら若かりし頃の父も関わっていたのではないか........私はふとそんな事を思った。
千さんが田舎を離れる数日前の事だ。私と妹は千さんにねだって、この地方で一番大きな町に連れて行ってもらった。バスに乗り込むと、車掌のお姉さんが千さんに恥じらうような笑顔で挨拶した。千さんは都会の雰囲気を持っているので、一緒にいる私と妹も地元の乗客の興味ありげな視線を感じる。私達は空いていた一番奥の席に、妹を真ん中にして座った。妹は嬉しそうで、歌詞の不明瞭な歌をうたって私たちを笑わせた。おかっぱの髪を揺らしながら頭で調子をとりさえした。私は千さんに旅行みたいだねと言った。海を左に見ながらバスに一時間ほど揺られたが、私達は疲れを知らなかった。
町にはデパートがあってエスカレーターがあった。初めてのエスカレーターに私はおっかなびっくりで乗った。妹は脚が悪いので千さんに持ち上げてもらった。妹の身体を支えながら、千さんは「君たちが大人になる頃には動く道路もできるだろうね」と言った。私はエスカレーターって遊園地みたいだなと思いながら、降りるのが惜しくて何回でも乗りたいと思った。私と妹は町の様子の何もかもが珍しかった。千さんの住んでいる都会ってもっと大きいのだと聞いたが、どんな街なのかとても想像できなかった。
私達は食事をしたり買い物をしたり、昔はお城だったという公園を散歩したりした。公園の池の大きな鯉に妹は興味津々で、柵につかまったままなかなか離れようとしなかった。千さんはベンチに座ってタバコをくゆらせながら、気のすむまで見せてやろうよと言った。私も千さんの隣に座って一休みして、買ってもらったナッツ入りのビスケットを食べた。千さんがもうすぐ居なくなると思うと、胸なのか頭なのかはよく解らないけど、どこかに空洞ができるような気がした。一緒にいて窮屈さや居心地の悪さを感じない大人なんて、千さんが初めてだった。どこか頼り無さげだが、いろんな事を知っているし、人や物事を公平に見たり感じたりしている人だと思った。何事も決めつけないし、私や妹の言う事を、子供の言う事だと軽くあしらう事はなかった。
「千さん、またいつか帰ってくる?」
「さあどうかな、田舎で俺は暮らせないからね。俺の居場所はこっちにはないんだよ」
「僕も大きくなったら街に行けるかなあ」
「行こうと思ったら外国にだって行けるさ」
「でも僕が遠くに行ったら、母さんがきっと心配する」
「おいおい、いつまでも子供でいるつもりかい。君だってきっと家を出る時が来るよ」
千さんの言ったとおり、私は十八歳で上京することになったが、あの頃の私は、山の集落と小学校という狭い世界しか知らなかったし、自分が大人になる事や家を出る事など想像できなかった。千さんは、自分も君と同じような子供だったよと言ったけど、そんなものなのだろうか。千さんのような大人になれるのだろうか。自分と異なる見方や考え方を尊重できる人は、つまらない争いなどしないのだろうと、今にして思えばだが、私は千さんを通してそんなふうに感じていた気がする。
「千さん、お墓参りはもう終わりなの?」帰りのバスで私は訊いた。「お墓って恐くない?」とも訊いた。千さんは笑いながら、そりゃあ恐いさと大げさにおどけて言った後「でも好きだった人や大切だと思っていた人を思い出す場所だからね。本当はちっとも恐くなんかないよ」私も祖父の事を思い出して、そうだねと笑ってうなずいた。
千さんが帰る日に私はバス停まで送って行った。妹も一緒に行くと言い張ったが、母は脚の事を心配して泣きそうな妹をなだめすかした。庭を出る時真っ赤なダリアが咲いていた。母が春過ぎに球根を植えたものだ。千さんは名残惜しそうに見つめていたが、よいしょとバッグを持ち替えて歩き出した。私達はしばらく黙ったまま、小川に沿ってゆっくりと坂道を下った。田んぼが多いので、この頃はまだコンクリートで舗装されていない川と用水路があちこち流れていて、蛍の幼虫や細長い巻貝のカワニナも多かった。笹舟をいっせいに浮かべて競争させたり、夏の暑さをしのぐために裸足で歩く格好の場所でもあった。
千さんは町へと続く広い田んぼの道で、すれ違う人みんなに軽く会釈をした。知ってる人なの?と私は訊いた。いや、今は何処の誰だか全く思い出せないけど、でもあの年頃の人って、子供の頃知っていた人達かもしれないからね。お世話になった人か、あるいはいじめた奴かは解らないけどね。千さんも、いじめたりいじめられたりしたの?そりゃあ、あるよ。嫌がらせだって、ケンカだってしたし、畑のスイカを盗ったことだってあるし、子供っていろいろな事をしでかすものだろ。
私達はバス停に着いてから二十分程待たされた。早めに家を出てきたから余裕がある。千さんは私にジュースを買ってくれて自分はタバコを吸った。父は葉タバコの栽培もやっていたが自分では吸わなかった。周りのおじさん達はみんなうまそうに吸っていたのに珍しかった。父が医者に止められていた事は後で知った。私も当時煙がうまいなどというのは変だなと思っていたが、千さんは食事の後やお酒の時には特に欠かせないらしかった。「確かに、これが無いと生きていけないというものではないけど、人が生きていくためには小さな楽しみが幾つか必要なんだよ」千さんはそう言って灰皿にタバコを投げ込むと、やって来たバスに乗り込んでいった。元気でなと千さんは手を軽く振ったが、私は何も言えずこくりとうなずいただけだった。家に帰る途中、真っすぐ帰らず脇道に逸れた。誰も見ていないのを確かめて、道端の畑から二個赤いトマトを盗った。どきどきしたが、それが不安なのか快感なのかも解らなかった。そして、私は自分でも解らない「何か」を振り切るように闇雲に走りに走った。
故郷の山と川だけは変わらずにあるけれど、町も人もすっかり様変わりして、今私は異邦人の気分だ。私の事を知っている人などまだいるのだろうか。私は80歳を前にしてまだ身体の動くうちにと思い、父や母の墓参りに帰って来たのだ。今回がおそらく最後になるだろう。脚の悪かった妹は結局治る事も小学生になる事もなく、富佐子さんと同じような血液の病ではやく逝ってしまった。東京で独り暮らしだった千さんの遺骨を私が引き取って、田舎のこのお墓に納めたのはもう二十年も前の事だ。すべての事がすっかり過去の物語になってしまった。
山際の集落は過疎化が進み、私の実家はすでに壊されて低い草木の更地になっている。私は星空を見たくて、泊まっている町の旅館を夕方抜け出してここに来た。町は明かりがあるので、あの頃の「本当」の星空は望めないからだ。私は昔住んでいた家の間取りを思い浮かべながら、柔らかそうな草地を選んで仰向けになった。土も夏草も昼の温もりをまだ保っていて、私は草いきれに軽く酔いを感じた。
子供の頃に見上げた夜空があの頃のまま、あまりにもそのままにあるので、私は自分が子供に戻ったかと錯覚してしまう。私は時間を忘れ、星空と懐かしい人達の思い出に浸りきる。過去と現在が混在して夢うつつのように、私はこの状態に幻惑されてしまっている。やがて、いつしかあのはるかな世界から星が降ってきた。初めは遠慮深く小雪のようにちらちらと舞いながら、そしてやがて満開の桜が散るように、鮮やかな光の粒が全身に降り注ぐと、柔らかく静かに......老いた私の目は濡れてくるのだ。
「尻尾の憂鬱」
窓の外を見ると、庭の木の枝に張られた蜘蛛の巣が見えた。雨上がりだ。蜘蛛の巣はいくつかの水滴を乗せた半透明なハンモックのようだ。持ち主の蜘蛛の姿はなく、朝日にきらきら輝くそれは小さな別天地だ。水滴の中にもさらに小さな世界が息づいているようで、ボクは眠気の残る目を擦りながらもじっと見入ってしまう。妙に気になったので、水滴を近くで見ようとそっと庭に出てみた。日曜の朝まだ早いので家族も町も寝静まっている。庭に出るのはひさしぶりなので近所の視線が気になる。
透明な水滴の中を注意深く覗き込んでみた。するとその中で、尾びれの長過ぎる不格好な魚が立ち泳ぎをしている。真っ白な魚で尾びれだけがオレンジ色だ。泳ぐのにかえって邪魔になるような、ひらひらのフリルのようなその尾びれから目を離せなかった。哀れむ気分と同時に、笑いたくもあって妙な顔をしていたかもしれない。そんなボクに気付いた魚は、ここから出してくれと言った。酸素が不足してしまって、もうこれ以上こんな狭い所では生きられないんだ。それにこの水滴がいつ蒸発してしまうか、蜘蛛がいつ襲ってくるかなど気が気でないんだと。
ボクは、君の言う事はもっともだと言った。でも、いくら君が小さいからといっても、こんな狭い所に住んだ事自体が間違いだったね。その長い尾びれもその中では随分窮屈そうだもの、とも言った。魚は、自分が望んでこんな姿でここに居る訳じゃないと不満そうに言う。その声は小さかったがはっきりした口調だった。そしてまた続けて、大体次のようなことを早口で喋った。
自分の産まれる場所なんて選べない。大きな河で産まれるか、道端のどろんこ水の中で産まれるか、こんな儚い水滴の中で産まれるか。人間だってそうだろう。大都市で産まれるか、電気さえないジャングルの奥深くで産まれるか。時代や国も、それに両親や家族なんて深刻で親密な環境も選ぶ事などできない。性別だってそうだ。肌の色も白か黒か黄か赤か、はたまた透明か。自分の意志で、望み通りの姿で産まれてきた者なんか世の中にはいないのだ。そんな当たり前の事をアナタは忘れているのか。
もしアナタが何処かの難民キャンプに産まれていたら、あるいは満足に教育も受けられない貧しい家庭で産まれていたらどうだろう?もし恵まれた資産家の家に産まれていたら、アナタは何を思うのだろう。駅のトイレや道路で働く掃除夫を下賎な者と蔑んだ目で見るのだろうか?アナタは先程からそれに近い目で、ずっと私を見ていたのではないか?
たまたまアナタも私も今の境遇で生きているに過ぎない。過ぎないと言うのは言い過ぎだろうか?いや、私はアナタの努力を認めない訳ではない。ただそれはゼロからの出発ではないと言いたいだけなのだ。スタート地点がそもそも違うのだ。アナタが今の位置にいるのは、そこにその姿で人として産まれてきたからという条件の上にこそあるんだ。
小さいから、産まれたばかりでまだ何も知らない何かの稚魚かと思っていたが、こいつは何でもお見通しらしい。でも、こんな反論する気にもならない「正論」を、さも自分独自の考えのように声高に主張する奴を、何者であれボクは好きではない。しかもボクに助けを求める立場にある奴に、偉そうに言われる筋合いはない。ボクは聞きながら舌打ちした。そんなことくらい解ってるさ。ボクだって.....と言いかけたがむなしい気分で止めてしまった。同情を誘うように自分の身の上話をする趣味は、ボクには無い。
もうそれ以上「演説」を聞く気になれなかったので、台所に戻りビールジョッキに水を入れた。そして、水滴からジョッキに魚を移し代え住処を広くしてやった。水滴の中に住むような、見過ごしてしまいそうな小魚には広過ぎるくらいだ。小魚と呼ぶのさえためらわれる超ミニサイズだ。ボクは机の引き出しの奥から虫眼鏡を取り出して見ている。長過ぎる尾びれをやっと自由に動かせるようになったのに、そいつは、まだまだこれでは不充分。いずれはここも狭くなる。そう言いながら不満そうに胸びれを横に振った。
ボクは、それなら大きな川に連れて行ってあげようと言ってはみたが、川まで流れて行くであろう庭の側の下水にそいつを流してしまった。ボクにとって川まで出かけるのは厄介な事なのだ。いや、それは事実ではあるが言い訳かもしれない。冷酷なとまでは言えないが、その時少なくとも意地悪な自分であった事を認めないわけにはいかない。ボクはこの魚を見ているのが嫌になったのだと思う。自己嫌悪のような自己憐憫のような、いらいらした気分になってしまったのだ。
何故って......告白してしまおう。部屋から出る時はズボンの中に押し込んで隠してはいるが、実はボクは、尻の後ろに..............長くて毛深い尻尾を持っているんだ。アイツと同じで無様な異様な身体なのだ。いや、同じというのは違う。少なくともまだアイツの方がマシだろう。いくら形やバランスが悪いからと言っても、魚に尾びれがあるのは当然で、まったく必要の無いボクの尻尾とは違うのだ。
誰にも相談せずに会社を突然辞め、引きこもりの生活を始めてから半年後に尻に突起物ができた。それが一年後にははっきりした尻尾の形になってきたのだ。三年目の今も成長を続けて60センチ程になっている。閉じこもって部屋から出ないボクに両親はあれこれうるさく言った。そんな両親を前に、ズボンを降ろして初めてこの毛深い尻尾を見せつけた時だった。ほら、よく見てみろよ。こんな身体でまともな社会生活ができる訳ないだろうと、大声で怒鳴ってやった。ずっと秘密にしていた尻尾を、これ見よがしにさらけ出すのは意外な程快感だった。だがボクは悲しみと怒りの演技をしながら部屋に戻り、荒々しくドアを閉めた。
ドアの向こうで母の泣き声が聞こえていたが、しばらくして気を取り直した父が、病院に行って診てもらえと言った。そんな物手術で切り取れるだろう。普通の身体になったら働け。あまり期待してない調子の張りの無い声が聞こえた。ボクは笑いたくなった。この尻尾を理由にまだまだこの生活を続けられるだろう。そんな事を考えたが正直に言うと不安でもあって、笑いはひきつってしまった。我ながらなさけない奴だとも思っているのだ。
ボクはあの魚を下水に流した事を少し後悔した。部屋には熱帯魚を飼う予定だった水槽、ろか器、照明、ヒーター、サーモスタットなどがあるのだ。この水槽でならあのチビを飼う事ができた筈だ。人と話す気はないが妙な生き物同士、アイツなら話し相手になったかもしれない。生意気だが案外いい奴だったかもと思った。少なくとも、世間体ばかり気にしておろおろしている両親よりはマシな相手だっただろう。父は患者に慕われる親切な歯科医師で、母は才色兼備な大学教授だと世間では言われているらしいのだが、家庭ではただの父と母だ。
妹はファッションとダイエットと恋愛にしか関心がない。髪の色もよく変えるし、 ネイルアートだか何だか知らないが、その長い爪先のケバケバしいデコレーションは何だ。掃除、洗濯、料理、家事一切できませんと公言してるようなものじゃないか。そんな知性を感じられない妹と話すより数倍良かったかもしれない。この妹はボクの尻尾を初めて見た時、ブルーのカラーコンタクトレンズの目でしばし凝視した直後に、信じられなーい!と手をたたいて大笑いしやがった。この時妹は金髪だったので、日本語のうまい外国人を相手にしている気分だった。
ボクは自分の部屋からあまり出ないので、たまにしか妹と顔を会わせない。ある日、いつも通りゲームとインターネットと読書の後で、喉の渇いたボクは台所でアイスコーヒーを飲んでいた。そこに帰って来た妹がちらっとボクを見ながら言った。いつもなら珍しい動物に出くわしたような表情で、何も言わず自分の部屋に向うのに、また新しい彼氏でも見つけたのだろう機嫌がいい。
「アニキもさあー、彼女とかつくったらいいのに。外に出るのが楽しくなるよ。イケメンまではいかないけど悪くないし、そこそこいけるよ」以前はボクの事をお兄ちゃんと呼んでいたのに、今ではこんな親しみのない呼び方をするのだ。ボクはわざとらしくニコニコしながら言った。「そいつはいい考えだ。ふさふさした長い尻尾のあるかわいい彼女を紹介してくれよ」
ボクは個性的な人に憧れながらも、あまり目立つのもイヤだと思っていた。妹みたいに虚栄心丸出しに自分を飾りたてるなんてイヤだ。今の自分はある意味超個性的だ。こんな身体的な個性など要らないのだ。そもそも人が尻尾を持っているなんて個性的ではなく、むしろ生物学的進化論的異常と言うのが当たっているのだろう。自分でも解っている。尻尾の付いた引きこもりの30歳の男なんて最低だ。いまの状態から抜け出せない理由として尻尾を口実にもしているが、正直なところこれから先どうしたものかと迷っているのだ。
こんな生活を始めてからテレビというものを見ていないが、ラジオはたまに聴く。音楽の合間にニュースをやっていた。小学生が近くの川で珍しい魚を捕まえたらしい。子供みたいにはしゃぐ耳障りな声で、若い女のリポーターが喋っている。リポーターが言うには、魚は真っ白でカワイイ顔で体長30センチ程で、オレンジ色の尾びれが異様に長い、と言った後でカワイイを連発した。
歯の無い長寿のお年寄りも、鼻のつぶれた犬も出来損ないのゆるキャラもカワイイで片付けられるから、若い女性のコメントは信用できない。小学生によると、まるで自分から網に入ったかのように關単に捕まったらしい。泳ぐというよりクラゲのように漂う感じだったようだ。水族館の飼育係の男が嬉しそうに、ぜひ我が水族館でこの新種の発見を特別展示したいと言っていた。
たぶんアイツだ。あのアンバランスのまま大きくなったのだろう。それにしてもアイツどこまで大きくなるのだ。ちっぽけな奴のことだから他の魚の餌食になったか、あるいは下水で傷ついて、川まで到着できなかったかと思っていたので内心ほっとした。それにしても、確かにあの姿では泳ぎづらいし、エサを獲ることも容易ではなかっただろう。プランクトンでも食べていたのだろうか。でも、初めて見た時はアイツ自体がプランクトンみたいなものだったが。
とにかく水族館で飼われる事になるとまずエサの苦労はない。それにまさかいきなり天敵と同じ水槽に入れられる事はないだろうし、生きるため、長生きするためには安全な水族館はいいのだろう。そんな事を考えながらベッドに寝転んで、尻尾をブラッシングしながら(やわらかい特級豚毛を使用!熟練職人が手植え植毛法で丹念に植毛したブラシだ)、さて自分はどうしたものだろうと思った。いつまでも両親に「飼われている」わけにはいかないのだ。
ボクは尻尾に対して違和感があった頃の事を忘れている。もうすっかり自分の身体として馴染んでいるのだ。今のボクは尻尾の毛並の手触りを楽しんでさえいる。髪の手入れをするのと同じように毎日シャンプーとトリートメントを欠かさない。家族と顔を会わせたくないので、風呂には深夜みんなが寝静まってから入る。外出しないのだから不潔でも汚くても構わないのだが、風呂は唯一ボクの一日のけじめとしての役割を果たしている。風呂の時間がなかったら、一週間もひと月もゲームやインターネットなどの連続に過ぎないだろう。酒が飲めないので、風呂上がりのアイスコーヒーを飲みながら一日の終わりを確かめるのだ。
しかし、それよりもとボクは思った。自意識過剰な、対人恐怖症がボクを風呂に向わせるのかもしれない。それがいつでも身ぎれいにしておくように、誰と会うわけでもないのにボクに仕向けているのかもしれない。妹がいつか言ったひとことも心に引っ掛かっている。ある日妹は廊下でボクとすれ違う時、なんだかケモノ臭いと言った。自分では自分の体臭に気付かないが、尻尾のせいかと気になった事がある。それ以来ボクは自分でも神経症かと思うほど、口臭対策としてはマウスウオッシュを欠かさないし、身体は勿論のこと尻尾を実に丁寧に慎重に洗うようになった。下着だって靴下だって毎日取り替えるし、ケモノ臭いなんてもう誰にも言わせない。
ボクの日常は潔癖であるべきなのだ。部屋は勿論、机の上にも無駄なものは置かない。置いてあるメモ帳に書き込んだあとのボールペンは、使った後は必ずティッシュで先を拭き取る。カスが溜まって文字がかすれたりするとうんざりしてしまう。まさかこんなボールペンを他人に貸せるわけがないなどと、有り得ない余計な心配をしてしまう。いつも一人きりなのに。部屋の掃除は毎日で、整理整頓はしているし消臭スプレーに除菌も完璧だ。本棚の本もCDも決まった位置にぴったり収まっているし、毎日ウエットティッシュで拭き取っているからパソコンやキーボードにホコリなんて無い。
ボクもいずれは自立しなければならないが、自分にどんな仕事ができるか解らないし、未来の人生設計などまだ全く考えられない。まずは家から普通に出られるようになる事だ。混雑する電車で通勤していたことがあるなんて、会社や町であんなに大勢の人達の中に居たことがあるなんて、今は遠い夢だったような気がする。ボクは先日近くのコンビニまで思い切って出かけた事がある。道行く人達が皆ボクの事を不審そうに見ている気がした。猜疑心に満ちた町を素っ裸で歩いているような居心地の悪さだった。恐怖心にも近いものだった。頭では解っているのだ。誰も他人の事などいちいち気になどしていないのだと。しかし、駐車中の車の中から家の陰から、郵便ポストや電柱から、町中あちこちから浴びせられる視線の攻撃にボクは危うく撃沈しそうだった。
マスクをして顔を隠しながらなんとかコンビニにたどり着いて、コーラとサンドイッチを手に入れた。店員は慣れないアルバイトらしく、お釣りを渡す時十円玉を落とした。彼はすみませんと謝ったが、目が合うとボクはどぎまぎしてしまった。何故か自分が失敗したような気になったのだ。外の人間とひさしぶりに顔を会わせると緊張してしまう。こんな視線恐怖症を克服しなければ社会復帰など到底望むべくもない。
ボクは試しにポートレイト写真を相手にしてみる。カメラを真っすぐに見つめている人物の写真が良い。どうせならきれいな女性を選ぼう。ボクは写真集のページを切り取って額に入れる。そして、椅子に座った状態で一番よく見える高さに調整して壁にかける。彼女は微笑みながら大きな瞳でボクを見つめ、ボクも恐れる事なくじっと見つめ返す。生身の人ではないからボクが視線を逸らさない限り彼女が目をそむける事は無い。ボクは頬杖をついたり髪をかきあげたり、チョコレートを口に入れたりしながらずっと見つめ続ける。ボクは彼女に話しかけ、彼女がどんな返事をするか聞き取ろうとする。どんなくだらない話でも、彼女はボクを有りのままに受け入れてくれる。これはボクのささやかなリハビリのひとつ。効果の程は解らないが。
ボクはあの魚の事が気になって、水族館のサイトを時々覗いている。アイツの事だから自分の待遇について、あるいは自分や仲間達を見せ物にしている水族館という施設について「演説」をしているかと思っていたのだが、最初からそれらしい情報が何もない。水族館側が不利な情報を隠しているのかとも思ったが、とにかくボクは少し心配になっている。
住む環境が変わった事で、アイツ失語症にでもなったのではないか。あるいはボクが下水に流した事が原因で、川まで流される途中あちこち身体をぶつけて、身体の麻痺や言語障害など起こしてしまったのではないか。小学生に關単に捕まったのは、泳ぎづらい不格好な尾びれのせいだけではなかったのかもしれない。考えてみるといろいろと思い当たるふしがあるのだ。
それにしてもだ。アイツが言葉を無くしてしまったとしたら、それはそれで良かったのかもしれない。尻尾を持っている自分や言葉を持っている魚なんて、仲間とうまくやっていけそうにはない。差別されるのがオチだ。いつの時代、どんな社会でも、何かしら差別の種を見つけるのにめざとい人がいて、それにまたすぐ同調する人がいるものだ。人が一人では生きられない存在だとしたら、「群れ」る事で生きる存在だとしたら、「群れ」が安定して存続するために異質な者は排除されるか差別される。ボクは妄想するのだが、学校で生徒ひとりひとりにシミュレーションとして、差別されいじめられる側の様々な経験をさせるべきだ。まったく........なんて笑えない冗談だ。
サイトの情報によるとアイツの成長は驚く程だ。それも身体の成長より尾びれの成長の方が著しい。現在の体長は60センチだが、そのうちの40センチが尾びれなのだ。ホルモンの異常か病気か。金魚の変種か鮒の突然変異か、異種間の掛け合わせか、宇宙からの飛来か、はたまた古代魚の生き残りかと議論がなされているらしい。当人にとってはそんなのはどうでもいい事だと、尻尾を見つめながらボクは思うのだ。ボクやアイツがこんな身体で生きている、ただそれだけだ。学術的な議論や研究の対象になるなんて、そんな事はこちらの知った事ではない。
実は魚の事よりも、最近自分の身体の変化が気になっている。尻尾の付け根から徐々に背中に向けて体毛が濃くなりつつあるのだ。すね毛だって薄い方だと思っていたが密度が増しているし、ひげ剃りも今までより時間がかかるようになった。ボクは尻尾を持つケモノに相応しい身体になりつつあるのだろうか。尻尾のある人間より、尻尾のあるケモノの方が自然だ。ボクはいずれ尻尾に乗っ取られてしまうのだろうか。
身体だけならまだしも、心まで徐々にケモノになりつつあるとしたらどうだろう。父の言う、尻尾を切り取って「まともな人間」になる事自体をを拒むようになるかもしれない。そうかもしれない。以前よりボクが極端に人の目を恐れるようになったのも......ケモノとしては自然だとも思えるのだ。
会社で働いていた頃は、仕事を終えて帰るとまずテレビをつけた。ニュースもドラマもサッカーもコマーシャルも抵抗無く見ていた。と言うより、むしろ積極的に同僚や友人達と、取引先でもテレビの情報を話題にして、共有することで安心していた。同じような価値観を持つ事無しに生きづらいのは、どんな共同体や社会でも同じだ。今にして思うと、ボクは相当無理をして周りに合わせていたような気がする。何と切ない帰属意識なんだろう。
テレビは現代に生きる我々を優しく、それと感じさせぬほどソフトにコントロールしている。ボクがテレビに興味がなくなったのは、画面に映し出される映像が自分と繋がりの無い別世界のようで、自分にとって少しもリアルでなくなったからだ。これは社会から脱落した者に特有の反応のひとつに過ぎないのか。それとも、ボクがますますケモノ化している証拠なのか。
ボクは時々、手入れの行き届いた尻尾に見とれることがある。そして、ボクはためらう。今この瞬間にも茶色の光沢のある体毛が、尻尾から背中に向けて這い上がりつつある。背中に微かなかゆみを感じてボクは後ろに手を回した。指に触れる体毛の柔らかさが何故か懐かしく心地良い。こんな風に感じるのは危険な兆候だ。今のうちだ。尻尾はすぐに処理すべきだ。父の意見は正しい。ボクはまだ理性を失っていないらしくそう思う。切るべきだ。
だが、そう思いながらも、気が付くと尻尾を揺らしている自分がいるのだ。無意識に........誇らしく揺らしている自分がいるのだ。
暑い日曜日、ビールを飲みながら短い「コント」を書いてみました。
「足音」
私と彼女は仕事帰りに待ち合わせて、行きつけの店で飲んだ。店はそろそろ混んで来る時間帯だが、顔なじみの店の若者がいつもの席に案内してくれた。静かすぎず騒がし過ぎず、程よい音量の会話や接客の声が聞こえる。私達は飲みながら最近読んだ本や、仕事の事や友人が旅行に出かけた事など話題にしていた。お互い暗黙のうちに、こんな場所での深刻な話題は避けている。もっともそれ程長い付き合いではないから、深刻な問題が二人の間にまだ無いのは幸せと言うべきか。
やがてほろ酔い気分で帰る間際に、そうだ、夕べあなたの夢を見たわと彼女が言った。私は関心無さそうに表情を変えなかったが、内心嬉しかったし興味津々だった。夢の中の私は彼女に愉快な作り話でもして笑わせたのだろうか。まずい創作料理でも食わせて吐かせたのだろうか。それとも甘く優しく抱きしめたのだろうか、あるいはクールな悪役として、泣いてすがる彼女を足蹴にでもしたのだろうか。
それで、夢の中での僕の役柄ってどんなものだったの? 私はグラスのワインを飲み干してから何気なく訊いた。ああ、それがね、あなたの姿は出て来なかったの。ただマンションの階段を降りる足音がしたの。あの足音は間違いなくあなたのだったわ。彼女は酔うと自信家になる。僕の出番はそれだけ? うん、それだけ。私は少々傷つく。
勘定を済ませて店の階段を並んで降りたが、彼女の靴音だけが私には聞こえた。私は靴を買う時歩いてみて、靴音のしない物を選ぶ事にしているからだ。
「俺達の列車」
母さん、そろそろ行かなきゃならないんだ。
列車はもうすぐ俺たちの町に着くだろう。
センジョウに向うための列車。俺と同じような連中、不機嫌な連中が詰め込まれた鉄の箱がお迎えに来るんだ。
父さんは酔うと再稼働の事を怒っていたね。原発の近くにあるこの町なんか、とても安心して住める所じゃないって。子供心に、俺もいずれはこんな町なんか出て行こうと思っていたさ。でも大人になって、こんなかたちで出て行くなんて思わなかった。センソウなんて誰が何の為に始めるのか俺にはさっぱり解らない。
きのう、あの娘に会ってきたよ。イクサに行くさ、戦士は戦死。くだらないシャレを言ったら、アイツ思いっきりビンタしやがった。痛かったよ。俺はお返しにアイツが痛がるほど強く抱きしめた。アイツ、痛いと言わずに何て言ったと思う。「アタシ、赤ちゃんができたの」......そう言ったんだ。
母さん、父親になるってどんな気持ちなんだろうね。俺には結局解らずじまいかもね。あの列車に乗った者で、無事に帰って来た奴はこの町にはいないからね。センジョウってどんな所だろう。聞いた話じゃ、晴れ渡った空からいきなり雨が降って来るような所らしい。
母さん、姉さんにも会ってきたんだ。子供の頃の懐かしい話をしたよ。姉さんに初めて聞いたけど、授業参観日に母さんが学校に来なかった時の事さ。先生が「子供と仕事とどっちが大切なのか」責めるように母さんにそう言ったらしいね?すると母さんは、もちろん子供が大事だ。だから大事な子供に食べさせるために毎日働かなきゃならない、そう言ったそうだね。女手ひとつで大変だったものね。
父さんも母さんも、センソウなんて知らない世代で良かったね。憲法が改正されてすぐに徴兵制の復活なんて、知らないままだったのは良かったよ。息子の俺が外国でセンソウを経験する事になるなんてね........知らずに良かったよ。俺もいろんな心配かけたけど、生死に関わる心配だけはさせずに済んだって訳だ。
じゃあね母さん。海の見えるこの墓地に、そのうち俺も戻ってくるさ。
もう行かなきゃ。列車はもうすぐ俺たちの町に着くだろう。
「ありどころ」
夜だ。僕はひとり満天の星空に向って凧を揚げている。上昇気流に乗った凧はS字型に揺れながら、遥か上空から僕を見おろしている。手元から伸びている糸は細くて、10メートル先の方は夜空に溶け込んでもう見えない。夜風はまずまずの勢いで、凧の黒い影は星空に四角い穴を穿ちながらまだまだ上空を目指す。
僕は糸を操りながらも、あの凧はもはや僕の所有物というより、宙に属する物のように感じている。上空の風の勢いが糸を持つ指に重く痛いほど伝わってくる。僕はひたすら凧を上昇させる。それだけを考え糸を繰り出している。糸はいつまで経っても途切れる事が無く、凧自身も自分の目的地や到達地点を知らない。ただ上に向う意志だけがあるばかりで、際限のない作業を僕に続けさせているのだ。腕の筋肉が痛み、重い荷物を担いだ後のように肩から背中から、脚までも疲れきってしまった。
どれほどの時間が過ぎ、どれほどの高みに凧が在るのか僕にはもう解らなくなっている。やがて腕や肩の痛みも麻痺してしまって僕はもう何も感じない。いつの間にか雲が夜空をすべて覆いつくし、凧の姿どころか何もかも見えなくなってしまった。月も星も無い漆黒の闇の中では糸の手触りだけが真実だ。この「蜘蛛の糸」にすがって登れたら...........僕は無垢な世界にたどり着けるだろうか。一瞬、そんな事を思った自分に苦笑しながら、ふっと自分の身体に視線を降ろしたが、静寂で艶やかな闇に溶け込んで、僕の姿は........何処にも無かった。
今年10回目の三人展にぴったり合わせて、ギャラリーの前の桜が見事に咲いてくれました。
今回の作品は縦長のキャンバスを使ってみました。
キャンバスの形を変えるだけで新鮮な気分になれるものです。



以前書いていたメモから
アートは日常の視点とはまた別の視点で見る事を示唆してくれる。日常のこまごました感情を絵画で表現したり再現しようとは思わないし、自分にはできるとも思わない。それらを表すのは文章の方がより相応しい方法だと思う。普遍的というのは気恥ずかしいが、僕は星空や海や大きな樹を見る時に感じるような、人が誰しも感じるようなある種の憧れや畏怖などの感情に類するようなものを表せればと思う。例えば古い遺跡が人類の営みや長い年月を想像させるように、自分の作品を見てくれた人の脳裏に様々な思いが広がる事を夢想する。
自分の作品は意志的で堅牢なものでありたい。同時にうつろいやすいもの、壊れやすく繊細なものも含んだものでありたい。言葉のうえでは、矛盾や相反するようなものたちさえも無理なく共存できる画面でありたいと思う。
自分は透明水彩のように「ピュアな色」よりも、例えばざらっとした抵抗感のある色、言い換えると「物質としての色」に惹かれる。古い壁や剥げかかったペンキや苔むした石などに見入ることがある。制作が進まない時は過去の自分の作品を見たりする。するとそれらが自分を後押ししてくれるし、自分を支えてくれている事に気付く。若い頃のように他の作家のやり方に直接影響を受ける事はもうない。だから、他の良い作品に出会えたら幸福な気分にゆったり浸るだけ。
(写真はクリックで拡大できます。)





 |
平原辰夫展2014.2.10(月)-2.15(土)11:00am〜19:00pm (最終日17:00まで) 祝日開廊 GALERIE SOL〒103-0027 中央区銀座1-5-2西勢ビル6F tel 03-6228-6050 ●東京メトロ有楽町線・銀座一丁目駅6番出口徒歩3分  作品画像および地図をクリックすると拡大されます |
2013年のページを見る
2012年のページを見る
2011年のページを見る
2010年のページを見る
2009年のページを見る
2008年のページを見る
2007年のページを見る
2006年のページを見る
2005年のページを見る
2004年のページを見る
2003年のページを見る